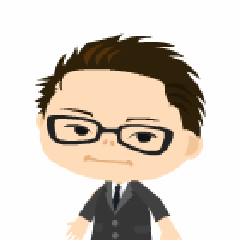先日から唐突に始めた「東照宮を巡る」旅。
忍東照宮に続いて訪れたのは、芝東照宮。
「忍」の次は「芝」です。
芝東照宮があるのは、以前、有章院霊廟や旧台院霊廟の門を観るために訪れた東京の芝公園。
都営地下鉄三田線「芝公園」駅のすぐ近くにあるのですが、なぜか間違えて一駅前の「御成門」で下りてしまいました。
天気に恵まれ、日差しが暖かく感じる日だったので、近くに見える東京タワーを横目に見ながら、ぶらぶらと散歩しながら向かいます。
辿り着いた参道の入口には、間違えようのないくらいに分かりやすい「東照宮」の社名標。
これなら、どんなにボーっとしていても通り過ぎる心配は有りません(笑)。
この東照宮に祀られている徳川家康公の木製座像は、家康公が還暦の時に彫らせ、居城である駿府城に祀られていたもの。
家康公の死後、遺言によって徳川家の菩提寺である増上寺に移されて「安国殿」という社殿に祀られました。
寛永10年(西暦1633年)、江戸幕府三代将軍の徳川家光公によって新たな社殿が建てられると、駿府城から移築された惣門や唐門、豪華な拝殿、本殿などが整備。
明治維新後の「神仏分離」によって増上寺から切り離され、単独の神社である「東照宮」として独立。
大正時代には重要文化財に指定されましたが、昭和20年の東京大空襲を受け、境内のほぼ全てを焼失してしまいました。
現在の社殿は、昭和44年に再建されたもの。
日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされていますが、境内は小規模で、鳥居のすぐ先に拝殿が見えます。
石鳥居に掲げられている「東照宮」の文字は、徳川宗家16代目当主である徳川家達氏の筆によるもの。
拝殿へと向かう参道の脇に、大きな御神木が立っていました。
東京都指定の天然記念物であるイチョウの樹。
江戸幕府三代将軍の徳川家光公が植樹したものと伝わっています。
昭和5年には国の天然記念物に指定されましたが、文化財保護法の改正により、現在では都の天然記念物となっています。
現在の社殿は、昭和44年に建てられたもの。
御本尊として、東京都指定の文化財である徳川家康公の座像が祀られています。
そんな拝殿の右脇に、小さな磐座が鎮座していました。
旭稲荷大善神、白鳥大善神、武吉弁財天の三柱の祀られた磐座は、つい最近の令和5年になって田村町(港区西新橋あたり)から遷座してきたものなんだとか。
徳川家と小田原北条氏の歴史に関係しているらしいのですが、それ以上の説明は書いていなかったので良く分かりません。