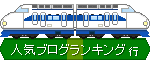今日も、ちょっと気になる稀有な語彙である。
稀有な語彙:欺罔(ぎもう)。
意味:
・人をあざむき、だますこと。。
筆者が触れた場所:行政書士講座で学ぶ。
用例:欺罔行為。
今回の語彙は、欺罔(ぎもう)である。
この言葉も、教わらなければ、わからない語彙である。
初めてこの言葉を知ったのは、行政書士講座の講義。
欺罔(ぎもう)。
これも、話し言葉では絶対に出てこない語彙である。
法律用語なのだろう。
大学で法律関係のことを学んでいれば、常識だったのかもしれない。
でも、「ロッポウ」と言えば、歌舞伎で役者が踏むものとしか認識がなかった文学部出身である。
全然チンプンカンプンだったのである。
ちなみに、念のため、ネットで意味を確認した。
小学館デジタル大辞泉だとこんな感じ。
き‐もう〔‐マウ〕【▽欺×罔】
[名](スル)《「ぎもう」「きぼう」とも》
1 人をあざむき、だますこと。
「俗に―さるるを一盃を喰うと曰う」〈服部誠一・東京新繁昌記〉
2 法律上、詐欺の目的で人をだまして錯誤に陥らせること。
精選版 日本国語大辞典ではこんな感じ。
き‐もう‥マウ【欺罔】
〘 名詞 〙 ( 「ぎもう」とも )
詐欺的行為で、相手に虚偽のことを信じさせ、錯誤させること。
あざむくこと。だますこと。きぼう。
[初出の実例]
「欺罔を戒め奸詐を禁じ」
(出典:明六雑誌‐一九号(1874)人間公共の説・三〈杉亨二〉)
[その他の文献]〔漢書‐郊祀志下〕
今回は法律文から引用(wiktionaryより引用)。
人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス(詐欺に関する刑法第246条第1項の改正前の条文)
現在は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」に書き換えられている。
何だかよくわからない。
要は人を欺く、騙すということの漢語的表現、法学的な表現ということか。
で、正しくは「きもう」と発音するようである。
多分、明治時代に「だます」ことを漢語的な言い方で表現したものなのだろうか。
その表現が、法学の中に入って行って、昭和の終わりまで残ってしまったということか。
これも多分、令和の時代の世界では、ほぼ古語で死語。
法学を学んだ人の頭の底に残る言葉と言えるか。