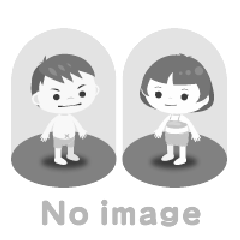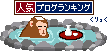少し前に、執刀医が在宅起訴されたニュースが流れていました。
兵庫県赤穂市の市民病院で2020年1月、手術中に適切な処置を怠り、患者に重度の障害を負わせたとして書類送検された40歳代の執刀医について、神戸地検姫路支部は近く業務上過失傷害罪で在宅起訴する方針を固めた。
複数の関係者への取材でわかった。
医師が医療行為で起訴されるのは極めて異例。
女性患者とその家族は、執刀医と市を相手取り、神戸地裁姫路支部に損害賠償請求訴訟を起こし、係争中。
執刀医は訴訟の証人尋問で、神経を傷付けた原因を問われ、「私の手術がつたなかったと思っている」と述べ、謝罪した。
一方で「手術をやってはいけないほどの技量ではない」とも述べた。
市民病院によると、執刀医が19年9月~20年2月に担当した手術では、女性患者を含め8件の医療事故が発生した。
同病院は女性患者の手術について医療過誤と認定。執刀医は21年8月、市民病院を依願退職した。
手術中にドリルで誤って神経損傷、重度の障害負わせる…赤穂市民病院の執刀医を在宅起訴へ : 読売新聞
とのことです。
非常に簡単に言うと、
「手術が上手くない医者が、たくさん手術をして、たくさんの合併症を起こした。」
という内容ですね。
この記事が事実なら、とんでもないことだと思います。
このニュースを見て思ったのですが、
「手術の上手・下手」
の判断というのは、なかなか難しいです。
このニュースでは、
「合併症が多い」=「手術が下手」
ということになります。
そうなんですが、
名医なほど、難しい症例の手術をすることが多いので、
データだけ見ると、
普通の術者よりも合併症が起きるリスクは高いです。
でも、その名医が
「リスクが高いから、難しい手術は控えよう」
と考えたら、困る患者さんがいると思います。
当然ですが、経験が少ない若い先生は、上手ではありません。
私は、若い先生をたくさん指導させて頂きましたが、
当時「う~ん・・・」と思っていた先生でも、
数年後、手術が非常に上手くなっていることも多いです。
どんな手術が上手な先生も、上手ではない時期が必ずあります。
その下手な時期を、上級医師が、
合併症を起こさず、
上手に導きながら、
次世代の上手な手術を育てることができるか?
ということが重要です。
患者さんからすれば、
「上手い上級医師がずっと手術をすればいいじゃないか」
という意見になるでしょうが、
人間は必ず年老いてしまうので・・・
「手術が上手いか、下手か」の客観的な判断基準は、なかなか難しいです。
手術時間が短ければ、上手いという訳ではありませんが、
非常に長ければ、やはり上手ではないでしょう・・・。
例えば、人工関節の術後、すぐに痛みなく歩けるようになったとしても、
たった数年で再置換が必要になるようでは、「手術が上手」とは言えません・・・。
以前、
「大御所の先生の執刀を辞めさせることも難しい」という話をしましたが、
術者からメスを取り上げる、というのは、なかなか難しいです。
手術ミスやトラブルが続いて、
院長から、その先生に手術を控えるように告げる、
というパターンが、主だと思います。
このニュースの医師は、本当に技量が足りていなかったのかも知れませんが、
よく考えると、
(長々と話しましたが、)
なかなか難しい問題だと思いました。