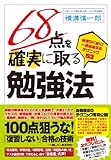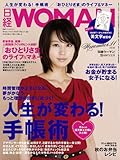横溝慎一郎行政書士合格ブログ
行政書士試験対策ブログ
プロフィール
最新の記事
テーマ
このブログのフォロワー
ブックマーク
お気に入りブログ
2025年03月24日(月) 14時04分35秒
行政手続法は丁寧に過去問学習をしていこう!
テーマ:行政書士試験戦略的学習法4月29日はGW道場
セルフチェックテストの第二弾という位置付けです。
zoomを使って5時間で一気に現状確認と弱点の把握をしていきます。
あなたの参加をお待ちしています!

行政手続法の学習
合格講座日曜クラスでは、昨日で「行政法(総論手続)」が終わりました。
ということで、今回は行政手続法について。
択一式において3問出されるのが通例です。
多肢選択式でも出されることはあります。
記述式は2006年以降3回出されています。
・2007年 7条
・2019年 36条の3
・2021年 36条の2
行政手続法は、ひととおり講義を受けた後が勝負です。
①申請に対する処分
②不利益処分
③行政指導
④届出
⑤命令等を定める手続
この5つが行政手続法の主要論点ですね。
もちろん、目的条文、適用除外(特に地方公共団体の機関との関係)もあります。
行政手続法は地方公共団体の機関が行う場合、適用が除外されているものがあります。
例えば、「知事が行う行政指導」。
これは、行政手続法の適用はありません。
「知事が審査基準を定める」とき、行政手続法上の意見公募手続は行う必要がありません。
これらは公正の確保や透明性の向上について努力しつつ条例でコントロールします。
「知事が廃棄物処理法に基づき行う産業廃棄物処理業の許可」を行うときは、行政手続法上の申請に対する処分の規定の適用があります。
産業廃棄物処理業の許可を取り消す場合も、行政手続法上の不利益処分の規定の適用があります。
住民基本台帳法に基づく転出届や転入届は市町村長宛にだしますが、ここには行政手続法の適用があります。
いずれにしても、これらの論点について、過去10年の本試験問題で何がどのように出されているのか?を、択一式だけでなく、多肢選択式や記述式も読んでいく。
これをやることで、講義で説明したことと過去問が有機的に結びつきます。
条文の文言のどこが特に重要なのかがわかってくる。
2019年と2021年の記述式は、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」の事例として必ず読んでおいてほしい問題です。
やみくもに条文を読んでもあまり意味はありません。
使われている文言にも目配りしましょう。
たとえば10条をみてください。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
最後の方に「その他の」というワードがありますね。
「公聴会の開催」は「適当な方法」の具体例のひとつです。
A、Bその他のC
このような並びになっている条文は少なくありません。
このとき、「その他の」のあとのCの代表例がAとBだよという関係になっていることを知っていると、条文理解の手助けになります。
これもそうですね。
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
「行政指導」の定義ですが、「行為」の代表例が「指導、勧告、助言」だと読み取れますね。
行政手続法はリサイクル率がとても高い科目なので、学んだことと過去問が有機的につながると、一気に得意分野にできます。
リサイクル率の高い行政手続法は、肢別になっているものを使うことも効果的です
その条文がどのくらい繰り返し問われているのか?を把握することで、自然と条文のなかに優先順位をつけることができます。
面倒くさがらずに、過去問と条文を突き合わせて丁寧にみていくこと。
行政手続法を得意にするために、あなたがやるべきことはシンプル&クリアーなのです。