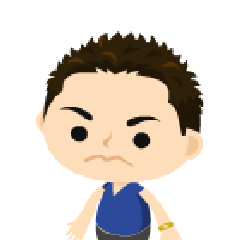プラントの非破壊検査をする上で効率の良い作業の進め方、および鉄則みたいなのがあるので紹介します。
全般
・移動は少なく、なるべく一筆書きで
プロットプラン(プラントの機器配置図)と渡された図面を見て、その日にどのプラントのどの機器や配管を検査するのかを把握して、回る順番を決めて、その順番に図面を並び替えてから現場に向かいます。
行き当たりばったりでやると、検査箇所を探しながら移動してあっち行ってこっち行って、さっき居たエリアにまた戻ってきて…みたいなことになって、無駄に移動の距離と回数が増えて時間と体力の無駄遣いをすることになります。
複数のプラントで作業をする場合は詰所から一番遠いプラントから手前に順番に片付けていくとかして効率良く回りましょう。
PT
・PTは上から下に
浸透液も洗浄液も上から下に垂れます。
何 mもある長い縦の油まみれの溶接線をPTするのを想像してみてください。
前処理時には上から下に汚い洗浄液が垂れます。
浸透液も濃く塗ってしまうと結構垂れます。
ということは、下からやると前処理が上まで終わった頃には下の方が全部汚くなっています。
除去処理をした箇所に上から浸透液が垂れてきます。
時と場合によっては洗浄液を直接ぶっ掛けてウエスで拭いて除去処理を行いますが、やはり浸透液混じりの洗浄液が垂れるので下の方が赤くなる+過洗浄(除去処理のし過ぎ)になります。
そういうことです。
これは縦の溶接に限った話ではなく、大きな物とか検査範囲の広い物等全部に言えることです。
・浸透液が垂れるのを利用する方法もある
浸透液を塗る範囲がめっちゃ広い場合に限った話ですが、刷毛に浸透液をたっぷりと染み込ませて塗る範囲の上の方にブワーっと塗っていきます。
そうすると最初の位置に戻ってきた頃には自動的に結構な範囲を塗ることが出来ている状態になっています。
ただ、たっぷり塗りすぎると範囲外の所まで真っ赤っかになってしまいますので、それを落とす作業が追加されます…。
その辺の加減は勘ですね…。
上手くやれば大幅な時間短縮に繋がります。
・乾拭きは大事
いくら範囲が広くても除去処理時の乾拭きは面倒臭がらずにしっかり行った方が最終的に楽です。
・動き回る場合は次に使う物を持って行動
例えば、新設の配管をひたすら追いかけて溶接部全箇所を検査する場合、区切りの良い所まで一気に前処理と浸透処理をして、除去処理をしながら戻ってきて、現像処理をしていって、判定と後処理をしながら戻ってきたりとかをする為に、ポケットや腰袋等に次に使う物を入れて行動します。
リュックサックに全部入れて前に抱えて常に持ち運んでも良いのですが、狭い場所があると面倒臭いんですよね…。
複数人居る場合は分かれてPTをやるとか、あるいは分かれずに役割分担を決めるとか色々出来ます。
MT
・MTは下から上に
PTとは逆です。
中でも特にプラントの非破壊検査でよくやる湿式の蛍光磁粉を用いたMTの場合です。
検査液は上から下に垂れます。
上から探傷すると、どんどん検査液が下に垂れて広がっていきます。
するとどうなるのかというと、大袈裟に書けば下の方はブラックライトを当てただけでめっちゃ黄緑色になります。
そんな状況で磁化して検査液を掛けてもきずが見づらいだけです。
だから、下から上に向かって探傷するわけです。
・探傷前に検査液をサッと塗る
これも湿式の話ですが、乾いた状態だと検査液を弾くというか上手くスーッと広がって流れていかないことがあります。
探傷前に検査液を含んだスポンジを絞ってサーっと撫でるように軽く湿らせておくと良い感じになります。
その程度であれば塗られた磁粉が原因で見づらくなることはありません。
・キャブタイヤの段取り
自分がどういう風に探傷を進めていくのかを考えてキャブタイヤを通す位置を考えるのも大事です。
「あの構造物のコッチ側を通したが為に長さが足りない」とか、もうちょっとで終わるのにケーブルの段取り替えが必要になったりすることがあります。
・タンクではキャスター付きの小さな台があると便利
キャスターを付けた小さな台等に装置やグラインダー等を載せると、探傷時にケーブルで引っ張られて全部ついてきてくれるので楽です。
・暗幕の畳み方
皆さんがどんな暗幕を使うのかは分かりませんが、私が居た会社の暗幕は上端部の真ん中に折り目だったか縫い目だったか忘れましたがそういう目印があって、一発目はそこと端を持ってバサッとやって、それから小さく畳んでいけばその場からほとんど動くことなく綺麗に畳むことが出来ました。
それを知らない人は一度全部広げて端と端を合わせて…と動き回って畳んでいました。