はじめに
こちらの記事をお読みになる前に
私のプロフィール
をお読みになってください。
※医療従事者からブロガーに転身!
ブログ講座を開催し、あなたの経済の基盤を作るお手伝いをさせていただいています。
お読みいただいていますあなた様へ。
以下のブログランキングへの
クリックをご協力よろしくお願い致します!
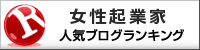
連載形式の
ストーリーをお届けしています。
【これまでのあらすじ】
私は看護学校に転職し、
先輩教員について
初めての実習にいきました。
そこでは、
看護学校の実習指導教員という
仕事の責任感の強さを
感じることになりました。
私は転職してからの2ヶ月間で
いくつかの実習に引率し、
先輩教員から
教員としての指導とは?
という視点で
オリエンテーションを
受けてきました。
その中で、
看護学校の実習指導教員の役割の1つに、
患者さんも、学生も、
どちらの安全も守ることを学びました。
実習という学習の場で、
看護師免許のない学生が
実際に患者さんの生活に入らせて
いただくことになるので、
学生の行動一つ一つに
責任を持ち見守る必要がありました。
安全を確保した上で、
学生が患者さんと関わりから、
最大限の学びが得られるよう
サポートすることだと認識しました。
そして2ヶ月が経った頃に、
最初の試練とも呼べる
実習がやってきました。
その中で次々と起こる出来事は、
ある程度していた予想を
はるかに超えており、
対処しきれない程でした。
私は1人でひとつのグループ、
3週間の病院実習を
担当することになりました。
初めて行く病院、病棟のため、
困った時にはすぐに相談できるように
別の病棟には
先輩教員が配置されていました。
担当したグループの学生は、
4年制学科の3年生で、
人数は6人でした。
学生は2年生の時に
基礎実習を終えており、
今回は専門制がより高くなる
領域実習を行う時期でした。
そして、この実習は、
12クールある内の、
一番初め、
1クール目の実習でした。
私は実習にむけての準備を
オリエンテーションで
習ったように行いました。
開始前には、
学生一人一人に対して面談し、
特性や個々の目標、
今までの実習での出来事や
学生自身の課題としていることを
確認しました。
コミュニケーションが苦手、
ケア技術が苦手、
疾患の理解が苦手、
記録記載が苦手、
と学生は様々な課題を抱えていました。
と、ここで、
実習病院の看護師であり、
実習指導担当者との
打ち合わせをさせていただいた際に、
初めて発覚したことがありました。
私が実習する病棟は
看護師の人手不足のため、
実習指導担当者の確保が難しく、
"常に学生を見ながら
一緒に行動できない"
認識でいて欲しいとのことでした。
すなわち、
私1人で6人の学生のスケジュールを
臨機応変に対応していくことに
なるのです。
・学生6人
・初専門領域実習
・病棟の実習指導担当者なし
・初めての病院
・ひとり立ち指導
これだけでも、どうやら
普通の実習ではなさそう
ということは想像できましたでしょうか?
そのような
イレギュラーな状況でしたが、
出来る限りの準備をして
この実習は始まりました。
ところが、
実習が始まると
次々と問題が起きていきました。
そもそも、看護学生の
実習という科目での目的、目標とは、
「患者さんの
疾患による、生活状況や
身体状況の変化を知り、
退院に向け
看護師が出来る
日常生活の援助を
行うこと」です。
そのため、学生は
バイタルサイン測定(検温)で
患者さんの全身状態の観察を
観て、聴いて、確認していきます。
また、
患者さんの疾患に対する思いを
コミュニケーションを通して
傾聴していくことで
身体面と精神面の情報から
全体像を把握していかなければ、
今抱えている問題に
辿り着くことは出来ません。
しかし、
学生は様々な理由をつけて
患者さんのところに
行かないのです。
例えば、
「リハビリをしていて部屋にいない」
「寝ていて起こすことが申し訳ない」
「食事、風呂、トイレにいっていて
タイミングが合わない」
等々の理由を述べていました。
しかし、"できない"
ばかりでは実習の目標である
患者さんのことが理解できず、
担当した患者さんに
合わせた援助もできない、
すなわち
実習目標が達成できないのです。
初めての専門領域実習ですが、
患者さんのところへ
いくことは
基礎レベルの行動です。
それを6人の学生が同じように
患者さんを理解できない
という状況に、
私の指導は
行き詰まっていくことになります。
1人1人の学生の意思、
実習の進捗状況を確認しながら
翌日までに行うことを約束すると、
翌日に休んでしまう
学生もいました。
毎日、
同じ病院内にいる先輩教員に
話を聞いてもらいながら、
また、学校で待機している
実習調整と呼ばれる
教員にも電話で相談していましたが、
解決の糸口がなかなか見つけられず
日にちだけが過ぎていく一方でした。
私は毎日
学生には何ができるのか、
病院までの通勤時間
片道2時間の電車の中でも、
家に帰っても
悩み続けていました。
すると徐々に睡眠時間が
削られていきました。
3週目、最後の病院実習の日には
病院に実習調整の教員もきていただき、
学生の実習中の様子を見てもらいました。
その時になって
学生達は焦って患者さんの元へ
行っていましたが、
最後の最後になって足掻いても
出来ることは少なく、
患者さんへの援助の実施にまで
至らない学生もいました。
最終日は学校に帰校し、
3週間を振り返りながら
実習のまとめをしました。
ここまで、なんとか
3週間の怒涛の実習は終了しました。
この実習を通して、
私自身の役割である
患者さんと学生の安全を守る
ことは出来ました。
しかし、
充分な学びが得られた
とは言えない状況でした。
病院実習が終了しても
まだやることはありました。
教員は実習の評価として、
点数をつけなければいけません。
学生一人一人に対して、
実習中の知識面、技術面、態度面、
大きなカテゴリーでは3つ、
その中での20項目を5点ずつ、
計100点満点でつけます。
合格点は6割以上
つまり、60点以上です。
この学生達のうち
2人の学生は、
学習面での理解度や、
実習の取り組み方、
目標、目的といわれる課題の部分である
援助の実施ができていませんでした。
さらに、
提出された実習記録を見ていくと、
完成していない状態でした。
採点基準に沿って評価をしましたが、
どうしても合格点をつけることが難しく、
不合格評価となりました。
この結果を、
同じ病院内で実習した先輩教員
にも相談しましたが、
その点数に納得していました。
私は、
なぜこのような評価になったのか
その理由を添えて、
実習領域のリーダーの教員へ
提出することにしました。
【次回予告】
私が初めて1人で引率した実習は
予想を超え、
1人では対処できない程の
凄まじさに驚きました。
学生2名が不合格評価となり、
その理由を添えて
リーダー教員へ提出した後に、
更に驚くことが待っていました。
人は頭で考えすぎてしまうと
先にすすめなくなってしまう
といわれています。
だからこそ、
あなたが想っていることをぜひ
私に教えてください。
そして、アウトプットすることが大切だとも
教えてもらいました。
私はその方法の1つとして
こうして自分の想いをブログに書くことを
実践しています。
あなたも、心にあるその想いを
ブログに書いてみませんか?
一緒に"今まで"と"これから"を
綴っていきましょう♪
