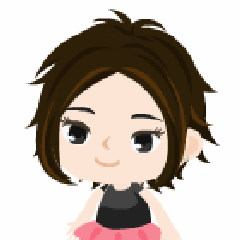「高額療養費制度」とは、保険診療の自己負担を抑えるための制度です。
その自己負担額を見直そうという議論が、昨年末から続いていました。
前回の見直しは、2017年~18年度でした。
その時は、70歳以上を対象に負担額の上限が引き上げられ、所得の区分も、より細かくなりました。
今回の見直しは、年齢を問わず、支払能力に応じて負担を求める「応能負担」を強める内容となっています。
しかしながら、この3月まで、ニュースが出るたびに議論が二転三転して、混乱された方も多いと思います。
これまでの一連の流れを、日経新聞の記事を通じて振り返ってみましょう。
そもそも高額療養費制度とは?
「病気にかかり、高度な治療を受けるなどして、医療費の自己負担が高額となった時に、負担を軽減する制度。
年齢や所得に応じて上限額が定められており、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その上限額と窓口負担の差額分を、健康保険組合などの保険者が給付する。」
※参考 高額療養費制度の自己負担限度額
(保険見直し本舗HPより抜粋)
・70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています(70歳以上の外来特例)
高額療養費制度の利用は増えている?
2021年度の件数は、10年前と比べて3割伸び、金額も4割増えた
その理由は?
・高額な新薬が相次いで保険適用され、医療費が高額となっている
・高齢化や生活習慣病の増加により、薬を継続的に使用する人が増えている
その結果?
「支払能力に応じて自己負担額を増やし、保険給付額を抑えることで、制度の持続可能性を高め、現役世代の保険料負担の軽減につなげる」
ことが求められる。
それでは、昨年からの日経新聞の記事を、順番に振り返ってみましょう。
2024年11月15日
「高額療養 負担上限上げ 厚労省 年内決定へ調整」
政府は患者負担額の上限を引き上げる検討に入った。2025年度にも実施の運びとしたい。
2024年11月20日
「高額療養費 年収で細分化 厚労省 上限額引き上げ」
政府は患者負担額の上限について、現在主に5つある所得区分を細分化する方針で、2025年度と2026年度の2段階に分けて実施する。各区分の引き上げ額は今後詰める。11/21の社会保障審議会の医療保険部会で制度改正に対する理解を進め、12月上旬をめどに方向性をまとめ、年末に詳細を詰める予定。
※ 現在の5つの区分とは
① 年収約1,160万円~
② 年収約770万円~約1,160万円
③ 年収約370万円~約770万円
④ ~年収約370万円
⑤ 住民税非課税者
の5区分です。
2024年12月4日
「高額療養限度額上げで保険料の負担減試算」
高額療養費制度に関する厚生労働省の試算が判明した。
各区分で一律に15%引き上げた場合、加入者1人あたりの保険料負担は、年1,200~5,600円軽くなり、全体では4,300億円減少する
5%引き上げた場合は、1人あたり年600~3.500円軽くなり、全体では2,600億円減少する。
「70歳以上の外来特例縮小」
厚生労働省は、高額療養費制度のうち、70歳以上の患者が外来受診し、医療費が高額となった時の自己負担の限度額を抑える特例(70歳以上の外来特例)の対象者を絞り込み、限度額も1,000円~2,000円引き上げる方針。
2024年12月17日
「高額療養費月8,000円上げ 厚労省が調整 年収370~770万円」
厚生労働省は「高額療養費制度」を巡り、1ヶ月あたりの自己負担の限度額を平均的な所得層(年収370万円~770万円)で、10%引き上げる調整に入った。
金額は月額約8万8,000円と現行より8,000円引き上げる。
年収の高い区分ほど、限度額の引き上げ率を高くし、住民税非課税世帯は負担が大きく増えないように、引き上げ率を年金の伸び率とそろえて、2.7%とする。
月内に具体案を固める見通しで、制度改正は早ければ2025年夏に実施する。
2024年12月18日
「高額療養費月3.8万円上げ 厚労省案 年収1,160万円超」
厚生労働省は「高額療養費制度」について、最も高い所得区分の1ヶ月あたりの自己負担限度額を15%引き上げる方針。金額は月29万円と、現在の25.2万円より約3.8万円高くなる。
他の所得区分に比べて、引き上げ幅を大きくしており、370万円~770万円では10%、770万円~1,160万円では12.5%の引き上げ幅(2万円アップ)とする。
早ければ2025年夏に実施し、2026年夏以降には、所得区分を細分化する方針。
70歳以上の外来受診での自己負担限度額も、2,000円引き上げる。
2024年12月25日
「高額療養費 月5.8万円上げ 年収650~770万円」
政府の「高額療養費制度」の見直し案が判明した。
2025年8月から3回に分けて、自己負担の限度額を引き上げる。
第一段階
25年8月 5つの所得区分を維持したまま、自己負担の限度額を2.7~15%引き上げる。所得区分が高いほど引き上げ率を高くする。
第二段階
26年8月 住民税非課税世帯以外の所得区分を3つずつに分けて計13区分とし、同時に、それぞれの上位2区分で限度額を上げる
第三段階
27年8月 同じ区分で限度額をさらに上げる
年収650万円~770万円の区分では、8.0万円→13.8万円と、現行より約5.8万円高くなる。最高の1,650万円の世帯では、25.26万円→44.4万円と、現行より約19.1万円高くなる。
「70歳以上の外来特例」の引き上げ
70歳以上で年収が370万円を下回る患者の外来受診に適用する「外来特例」は、26年8月に2,000円~1万円引き上げる。
「多数回該当」の制度で患者負担を増やす
年収650万円~770万円の区分で、2027年8月~4回目以降の負担額を今より32,400円高くし、76,800円とする。
この引き上げの結果、加入者全体の保険料負担は年間で3,700億円減る見通しで、1人あたりの保険料は1,100~5,000円軽くなる。
12/25にも、加藤財務相と福岡厚労省が折衝し、見直しが正式決定される。
さて、ここまで、どんどん進められてきた見直し案ですが、年が改まると、ストップがかかり始めます。
2025年2月6日
「高額療養費の負担増抑制 政府与党 修正視野に協議 治療抱える患者に配慮」
患者団体の反発や野党の批判を背景に、負担増の軽減に向けた協議が始まった。
4月の衆院予算委員会で、石破首相が政府案の修正を視野に協議。
厚労省では、多数回該当の引き上げ幅を緩和する方針が浮上した。
2025年2月15日
「長期治療 負担据え置き」
長期の治療を受けた患者については負担額を変更しないことが、福岡厚労相とがんなどの患者団体との面会で明らかなった。
「多数回該当」の限度額引き上げは見送り。
高額療養費制度では、過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回該当」となって、上限額が下がる仕組みがある。
現行では370万円~770万円の区分で、自己負担限度額は4万4,400円だが、これを7万6,800円に引き上げる案が検討されていた。
この引き上げは据え置かれることになった。
ただし、1ヶ月あたりの限度額引き上げは当初案の通り。
2025年2月17日
「長期治療の負担増凍結」
石破首相は17日の衆院予算委員会で、「見直しの凍結を政府として決断した」と発表
2025年2月28日
「高額療養費値上げ延期へ」
自民・公明両党は負担限度額の引き上げを延期する方針
多数回該当の引き上げの凍結だけでは不十分との立憲民主党の批判を受け、与党は27日に制度全体の引き上げを延期する方針を示した。
2025年3月1日
「高額療養費 今秋に判断」
2026年8月以降の引き上げを再検討する方向で、今秋までに判断する。
ただし、2025年8月の引き上げについては実施する。
2025年3月8日
「高額療養 引き上げ見送り」
石破首相は7日、負担限度額の引き上げなどの実施を見送ると表明した。
2025年8月の引き上げも見送ることとなった。
高額療養費制度の見直し案の変遷
当初案
2025年8月から27年8月にかけて、3段階で負担上限額を引き上げる
↓
2月14日修正
長期療養している患者に配慮して「多数回該当」の負担増凍結
↓
2月28日修正
3段階上げのうち、25年8月は予定通り引き上げ。
26年と27年は再検討
↓
3月7日修正
見直し全体をいったん見送り
このように、高額療養費制度見直しは凍結されました。
あらかじめ患者団体の意見を聞くなど、丁寧に議論を進めることなく、決定プロセスが拙速だったという批判もあります。
さらに、夏の参院選への配慮、少数与党の難しさなど、多くの問題が影響した結果となりました。
「応能負担」ということで、これまでも、高額所得者の負担増を求める改革が進んでいますが、今回の見直しは、年収770万円以下という平均的収入の現役世代にも負担を強いる見直しだったことも、大きな反発を生んだ要因と言えると思います。
2025年は「団塊の世代」が全員、75歳以上となります。
今後も予測される医療費の増大に対して、今後、どのような社会保障改革が進められていくのでしょうか。