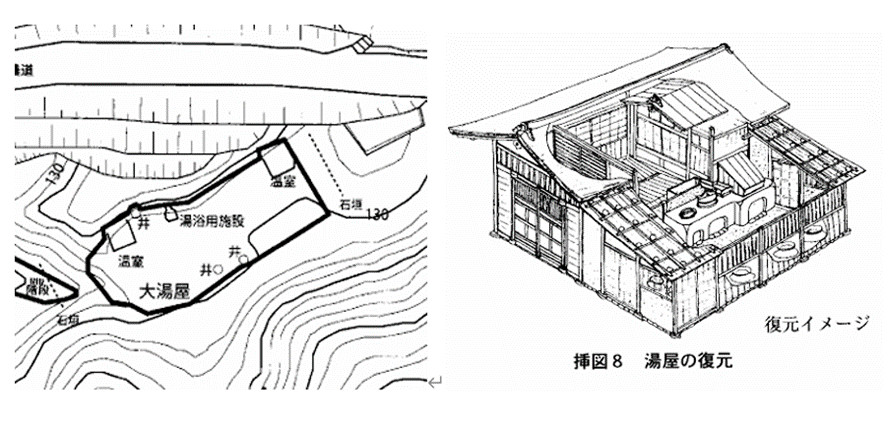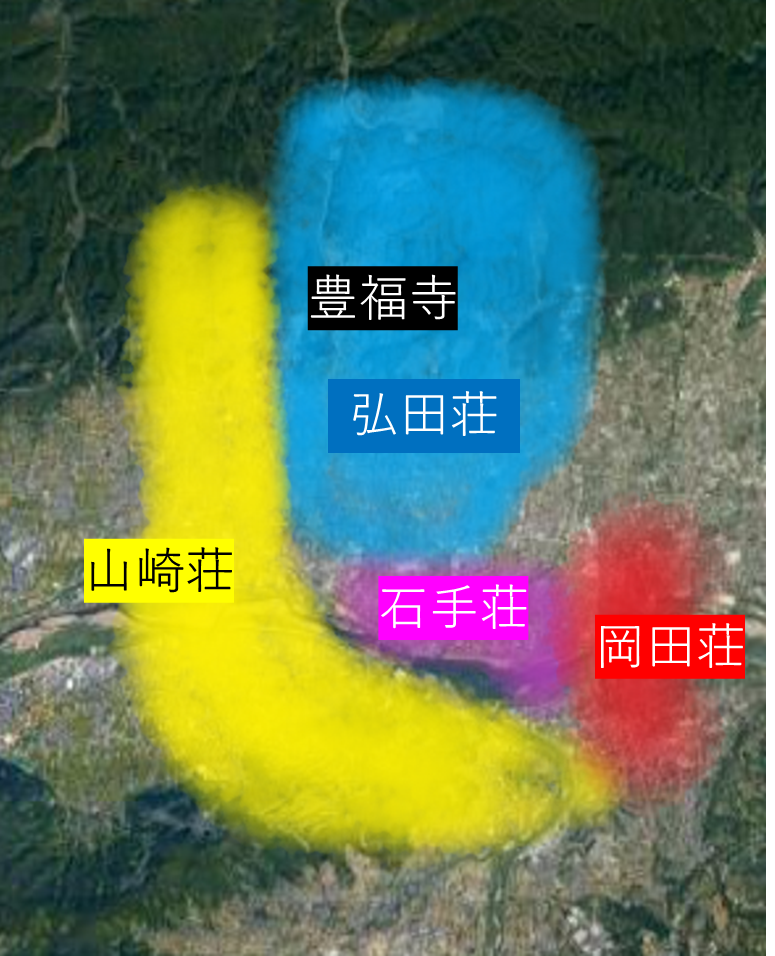称名はこの時点ではまだ、観想ができない人が浄土に往きやすくするための、次善の手段に過ぎない。しかしこの考え方が変わる契機となった書が院政期に出現する。その書の名を「観心略要集」という。
さて、そもそも天台宗の根本教義は「空・仮・中」の三つの真理で表わすことができる。この世の事物はすべて実体ではないとする「空諦」、すべて縁起によって生じた現象であるとする「仮諦」、すべては空・仮を超えた絶対的真実であるとする「中諦」、これらを総称して「三諦」と呼ぶ。そしてこの「空・仮・中」であるが、これはそれぞれ「阿・弥・陀」の三字に相当するのだ、旨を記したのがこの「観心略要集」なのである。
「阿・弥・陀」=「空・仮・中」であるということはつまり、称名念仏は「天台の三諦の真理を含む」行為であると考えられることになる。「阿弥陀仏」の称名を唱える行為自体に、意味が生じてくることになるのだ。こうして称名を唱える行為は、大いなる功徳を持つ念仏となった。
このように「阿弥陀仏」の名号を観想に結びつける理論を、「阿弥陀三諦説」と呼ぶ。(末木文美士氏による。)以降、叡山において「観想」と「称名」は「同等の価値を持つもの」として遇されていくようになるのである。
このように叡山内において、称名念仏の理論上の地位向上が進んでいったわけだが、民間においては称名念仏はどのように受け止められていたのだろうか?称名念仏というスタイルを民間に流布させた代表的な僧として、「市聖(いちのひじり)」とも呼ばれる、空也がいる。
空也は前記事で紹介した、源信とほぼ同時期の平安中期に活躍した人である。肩から下げた金鼓で拍子をとりつつ「南無阿弥陀仏」の名号を唱え、各地を回って勧進を募った。井戸を掘り、道を切り開き、橋を架けるなど、各種基盤インフラを造るプロジェクトを幾つも立ち上げ、人々のための社会事業に邁進したのである。その法会では、集まった人々に念仏を唱えさせていた、とある。

空也はどのような意図で、念仏を唱えさせていたのであろうか。当然、浄土思想に基づいた「極楽へ導くための次善の手段」としての称名念仏を指導していた、と思われるのだが、民衆の受け止め方とは若干乖離があったようである。
当時の仏教は、おしなべて密教的要素を土台としている。台密・東密の両者は勿論のこと、南都仏教でさえその影響を大きく受けている。そして密教は現世利益を求める方向性の教えであったから、「加持祈祷」という行為を生み出した。その大なるものが朝廷が主導して行う「国家鎮守」で、疫病の流行を鎮めるものや、地震などの天災に見舞われないようにするものなどがある。その最も大規模なものは、博多に蒙古が襲来した際に行われたもので、国を挙げての大規模な調伏が行われている。
一方、ここまでスケールの大きなものではなく「個人的な欲望を満たす」加持祈祷もあった。これがまた色々あって、出世を願うためのもの、政敵を調伏するためのもの、人を呪い殺すものなど、様々な加持祈祷があった。そして最も多用されたのが医療のためのものである。
当時の人が病気になったときの、正しい手順はこうである――まず陰陽師を呼ぶ。占いによってその原因を探る。その結果「原因がモノノケである」判断される場合がある。ここでいうモノノケとは「正体が定かでない気配」のことである。その多くは死霊や生霊だったりするのだが、その場合には僧侶による加持祈祷の出番なのである。
モノノケを調伏するための「不動法」や、モノノケを他人に憑依させ追い出す「憑祈祷」など、様々な祈祷のバリエーションが生まれている。こうした行為こそが、当時の一般的な医療行為だったわけだ。なお験者(げんざ)と呼ばれる、こうした僧たちの中で一番人気は、園城寺の僧らであったらしい。こうした方面に力を入れて営業していたのだろう。
こうした加持祈祷の文化は、民間にも浸透していた。そして称名念仏において「阿弥陀仏の名を唱える」行為は、「阿弥陀仏の絶大な力を働かせることができる、ありがたいおまじない」という風に受け止められたようだ。当時の一般民衆にとって、称名念仏は呪術的行為、つまり加持祈祷の延長線上として受け止められていた面が強いのである。入り口はどうあれ、こうした動きによって民衆に称名念仏が広がっていくのだ。
平安後期になると、民衆の間にもようやく浄土思想が浸透してくる。この時期、呪術としてではなく本当の意味で民間に称名を浸透させた人物として、良忍という天台僧の名が挙げられる。彼は「融通念仏」という名の運動を創始した。これは「1人が唱える念仏も、皆で一緒に唱えると、その人数分だけ唱えたことになる」というものだ。
称名念仏は、唱えれば唱えるほど功徳があると考えられていた。回数が多ければ多いほどいいのであるが、1人が唱えられる称名には物理的な限界がある。しかしこの考え方によると「一緒に100人で称名を1回唱えると、それに参加した人それぞれが、100回唱えたと同じ功徳が『融通される』」という、便利なシステムなのである。つまりこの会に参加する人数は、多ければ多いほどいい、ということになる。そんなわけで、この運動は大変な盛り上りを見せたのであった。
このように聖(ひじり)と称される、全国を行脚した彼らのような僧によって、民間に称名念仏が浸透していくのであった。(続く)

なおこの神泉苑においては、融通念仏の中興者・円覚上人による教えを無言劇とした「大念仏狂言」という芸能が今も行われている。なぜ無言劇なのかというと、昔は演者は能面の下で念仏を唱えながら演じていたから、という説があるのだ。融通念仏の教えを広めるために始められた芸能であるから、演者も観る方も念仏を唱えながらこれを行うわけである。なお神泉苑における「大念仏狂言」の歴史は比較的新しく、明治になって始められたものである。維新後、壬生寺において行われていたものが続けられなくなり、それを迎え入れる形で神泉苑にて行われるようになったのだ。壬生寺における本家の「大念仏狂言」は戦後に復活を遂げる。祭りや文化などの伝統は1回途絶してしまうと復活させることが難しいものなのだが、幸い神泉苑において途切れることなく続けられていたから、復活させることができたのだ。なので演者の殆どが、壬生寺と神泉苑の両方を掛け持ちする、とのことである。