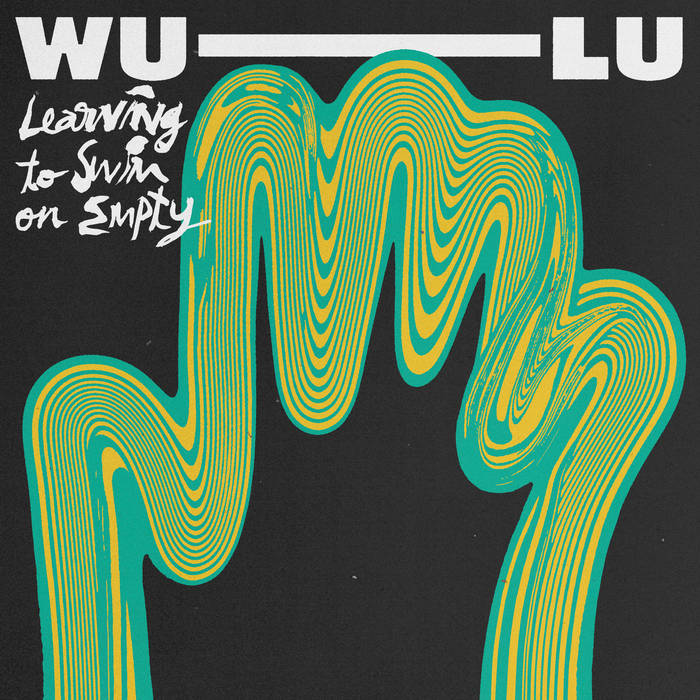Mdou Moctor 『Funeral For Justice』
 |
Label: Matador
Release: 2024/05/03
Review Oh France!
西アフリカのサハラ砂漠にほど近い地域にトゥアレグ族という民族が暮らす地域がある。彼らは白装束を身にまとい、そしてテントで拠点を張って生活しているらしい。しかし、そういった原始的ともいうべきアフリカの姿は今や幻想のものとなりつつある。アフリカの都市圏では、すでに2000年以降の東南アジアのような暮らしを多くの市民は送っており、彼らはデジタルデバイスを所有し、そして町中にはバスが通い、現代的な生活がごく普通になってきている。
そしてトゥアレグは、ある意味では音楽的な民族であり、このグループからはエムドゥー・モクターだけではなくティナワリンというグループも登場している。どちらも1970年代のヘンドリックス、グレイトフル・デッドを思わせるような古典的なロックバンドである。そして表向きのイメージではエムドゥー・モクターについてはヘンドリックスの再来というキャッチフレーズばかりが独り歩きする場合があるものの、グループの音楽的な魅力は、実はロックミュージックだけにとどまらない。彼らは、西アフリカの三拍子の民族音楽ーフォークミュージックを次世代に伝える役割を持っていて、それはこの最新作『Funeral For Justice』にも共通する事項である。もちろんいうまでもなく、そこには"タマシェク語"という固有言語の次世代に伝えるという意義もある。
すでに述べたように、アフリカ圏の国家のほとんどは、植民地化における辛酸を舐めてきたのは事実である。それは19世紀に始まり第二次世界大戦後の独立の時代まで表向きには続いた。この場合、単一の国家にその責任を負わせるのは残酷である。なぜなら、どのような国家もどこかの時代のおいて領土を広げようとしてきた経緯があり、それはある意味では国家の富を増加させようとする国家にとって避けられぬ運命だからである。しかし、国土としての植民地化という構図の他にも、”経済的な植民地化”という考えがある。換言すれば、金融支配下に国家や国民を置くという政治構造である。そして、この間接的な統治形態はそれ以降の時代も長期にわたって続いたのである。この旧態依然とした金融支配を断ち切るべく、アフリカ独自の金融市場を開放させようとしたカダフィが、どのような結末を迎えたのかはすでに多くの人々が知るところではないかと思う。彼は金融が命よりも重いということを身をもって知ることになった。2000年代以降の世界情勢において、永遠に続くと思われた欧米社会による金融支配であったのだが、近年、ロシアや中国の主導によるBRICSの動きにアフリカ諸国が賛同し、実際に参加している点を見るかぎり、古くは大英帝国や以降の米国が主導したような一強支配の構造はもはや過去の幻影になりつつあり、実際的に単一の通貨はその支配力を弱めているのである。
エムドゥー・モクターが台頭し、世界のロックファンがその存在を知るところになったのは、ある意味では必然的な流れではなかったかと思う。彼らは決して新しい音楽を提示するわけではないが、その中にはハードロックの普遍的な魅力があり、そしてエムドゥー・モクターのギターには瞑想的な響きがある。伝説となったのが、ニジェールの河畔でのライブセッションであり、彼らが演奏をしはじめるやいなや、周囲にいた生物がバンドの周りに集まってきたのである。そういった商品化されたものとは別のリアルな質感を持つロックミュージックは、パッケージされた音楽に対するアンチテーゼともいえ、またそれが彼らの新作アルバムの醍醐味でもある。ただ、エムドゥー・モクターの音楽を単なるエキゾチズムとして解釈しているうちは、バンドの本当の魅力に迫ることは難しいのではないだろうか。なぜなら、そこには先進国の市民としての驕りがあり、少なくともそういった異文化のものを下に見ている証拠なのだから。
こういったバンドが気を付けておきたいことは、その音楽が見世物やミュージカルにならない、ということである。なぜなら西アフリカの音楽はわたしたちが今まで知らなかったに過ぎず、わたしたちが生まれる前から存在していた。ただ、そのことを知らなかったという無知によるものなのである。そう考えると、マタドールから発売された「Funeral For Justice」は純粋なロックミュージックの魅力を体感できるのは事実だが、それと異なるポスト・リスニングが可能となる。つまり、ハードロックのリズムや高らかなギターの響きとは別に今までわたしたちがしらなかったものをあらためて再確認するという意味が求められるのである。いつもわたしたちは何かをよく知っているように装うが、実は、本当のことは何も知らず、無明の状態にある。ロックバンド、エムドゥー・モクターの音楽には、”平均化された音楽評価”とは別に、音楽をやることや演奏することの意義や、その動機のようなものが顕著なかたちで含まれている。
このアルバムには同じトゥアレグ族から登場した”Tinawarin”と同じタイプに属するハードロックソングが収録されている。その筆頭は、タイトル曲、「Sousoume Tamacheq」、「Imajighen」、「Tchinta」となる。これらのハードロックソングには、西アフリカの持つグリオの時代からの儀式音楽としての三拍のリズムや、ギターのフレーズ、固有言語が含まれている。上記の曲をリスニングする際には、ぜひ音楽だけではなく、歴史の香りを探してみていただきたい。さらに、今回のリリースで新しくプロデュースの側面で付け加えられたのが、エムドゥーモクターのロックソングを、エレクトロニック/ダンスミュージックの側面から解釈するという要素である。これらは、彼らの音楽が単なる往古の時代のものではなくて、今の時代に生きる音楽であることを示唆している。それに加えて、西アフリカ圏の民族音楽の色合いが加わる。いわば、エムドゥー・モクターしか生み出し得ない音楽が作り出されたとも言えるのだ。
なおかつ今回のアルバムでは、前作よりも民族音楽の要素が付け加えられ、エンターテインメントのような形、つまり、一般的に親しみやすい音楽として収録されている。「Imouhar」、「Takoba」、「Djallo #1」、「Modern Slaves」を聴くと、トゥアレグ族の生活がどのようなものであるか目に浮かんできそうである。彼らは、20世紀までアフリカの民族が奴隷の境遇に甘んじてきたことに関して、悲しみや憂いを交えることもあるが、そのことを悪徳であるようには思っていないらしい。なぜなら、それが悪となると、その立場にあった人々への冒涜になりえる。もっといえば、悲しみに沈んだ人々のスピリットが浮かばれなくなるからである。彼らは、アフリカの植民地の時代を踏まえた上で、この地域の代弁者となり、建設的で明るい未来をロックソングに乗せて歌う。「Oh France」は、彼らのアフリカ地域の宗主国であったフランスへの苦言もあるが、少なくとも、それらの二つの歴史に対して多大な敬意が払われている気がする。
85/100
「Modern Slaves」