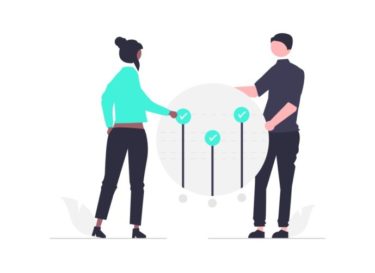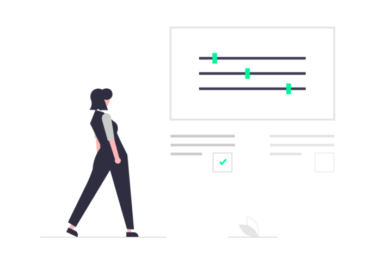労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条)。
その休憩時間に仕事が入ってしまったようなときには、別途の休憩時間の確保よりも、休憩時間が取れなかった時間数に応じて割増賃金の支払を希望する社員もいるのですが、これは適正な運用なのでしょうか。
❷分割付与や時刻をずらして付与するなどの方法がある
労基法で規定する休憩時間の与え方の基本
労基法で規定していいる休憩時間については、次の3つのルールに従うことが基本です。
3つの基本
2⃣一斉に与えなければならない(同条2項)
3⃣自由に利用させなければならない(同条3項)
運輸交通業の長距離乗務員や日本郵便(株)の一部の郵便業務従事者などは労基則32条により、休憩時間を与えないことも可能とされていますね。
そもそも休憩時間とは?
休憩時間とは、労働から離れることを保障されており、自由に利用することができる時間のことです。
あ
仮眠時間でも休憩時間に当たらない場合も
不活動の仮眠時間であっても休憩時間に当たるとは限りません。
裁判事例として、
ビル管理会社の労働者が配置されたビルで24時間勤務した場合に7~9時間の仮眠時間があったものの、警報が鳴った際の対応や電話接受などの義務が課されていたケースでは、
休憩時間の長さや回数上限はない
労基法では、休憩時間の長さの上限や回数の上限についての規定はありません。
長いことで拘束時間が不当に長くなるといった問題や、短い休憩を何回も細切れに与えるとした場合には、「労働から完全に解放される」とか「自由に利用できる」とは評価できないこともあり、むしろ「手待ち時間」と評価され得ることで、労働時間扱いになる可能性がでてきます。
あ
時間単位年休を取得した場合の休憩時間
◆時間単位年休の取得により1日6時間以下の勤務となったとき
労基法上は休憩時間を与えなくても違法とはなりません。
職場で混乱することを避けるために、時間年休取得により労働時間が一日6時間以内となった場合には、休憩時間を与えない旨の就業規則の規定で明確化を図ることが適当です。
あ
◆時間単位年休が休憩時間を挟むとき
年休は取得した場合に就労義務が消滅する(昭和48.3.6基発110号)ことから、就労義務のない休憩時間はそもそも年休対象とはなりません。
所定勤務時間帯のみが年休取得扱いとなります。 あ
あ
休憩時間は勤務開始や終了時刻と接続してはならない
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
「労働時間の途中に」とは、労働時間が6時間超えの直後や、8時間超え直後に休憩を与える趣旨ではありません。
一の勤務の労働時間の中途に与える趣旨であって、中途であればその位置は問わないとされます(労働法コンメンタール「労働基準法」)。
仮に、労働時間終了直後に、不足していた休憩時間を与え、その時間経過後に帰宅させるといった方法では、「労働時間の途中に与えた」とは言えませんので違法となります。
なお、労働時間が8時間を超える場合、どんなに残業時間が長くなっても8時間以下までに対する45分間と延長後の15分を合わせた1時間の休憩を途中で与えることで構いません(昭和26.10.23基収5058号)。
あ
あ
一斉休憩の適用除外
休憩は一斉に与えるのが原則ですが、労使協定で適用除外の範囲を決めたり、特定の業種の事業については、労使協定の締結に関係なく適用が除外されます。
あ
1⃣労使協定により一斉休憩を除外できる
労使協定の締結により一斉休憩の適用を除外する労働者の範囲などを決めることができます。
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合には労働者の過半数代表者)との書面による協定があるときは、協定で定めた範囲で一斉に休憩を与えないことが可能です(労基法34条2項)。
書面による協定
協定には一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について定めなければなりません(労基法15条、平成11.1.29基発45号)。
あ
2⃣一斉休憩が適用されない事業
事業の性格上、現実に一斉休憩が困難なものもあります。
そこで、労基法40条により休憩に関する規定について、省令で別段の定めをすることができるとされています(労基法40条、労基則31条)。
具体的には、次の事業については、一斉休憩の適用は除外されています。あ
あ
休憩時間は自由に利用
休憩時間とは、労働から離れることを保障されており、自由に利用することができる時間のことです。
しかし、休憩時間は拘束時間中の時間であることから、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないとされています(昭和22.9.13発基17号)。
あ
自由利用については絶対的なものではなく、相対的なものに過ぎないと言えます(コンメンタール「労働基準法」上)。
あ
休憩自由利用が除外される者
業務の特性により、いくら休憩時間とはいっても自由利用が認められないものもあります。
警察官、消防吏員、児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員などには休息時間の自由利用については適用がありません(労基則33条)。
あ
まとめ
休憩時間は、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」であるという労基法の趣旨を理解することが重要です。
休憩時間を賃金・割増賃金で代替することができませんので、労働者の健康確保、業務遂行のメリハリ等による業務効率化の観点からも、どのような状況下にあっても少なくとも労基法上の休憩は確保するということが必須です。