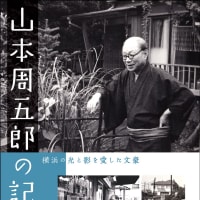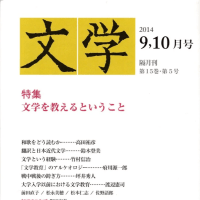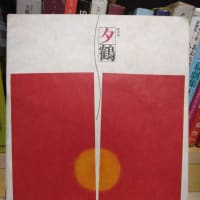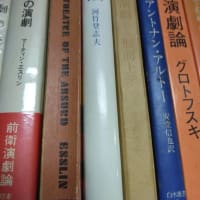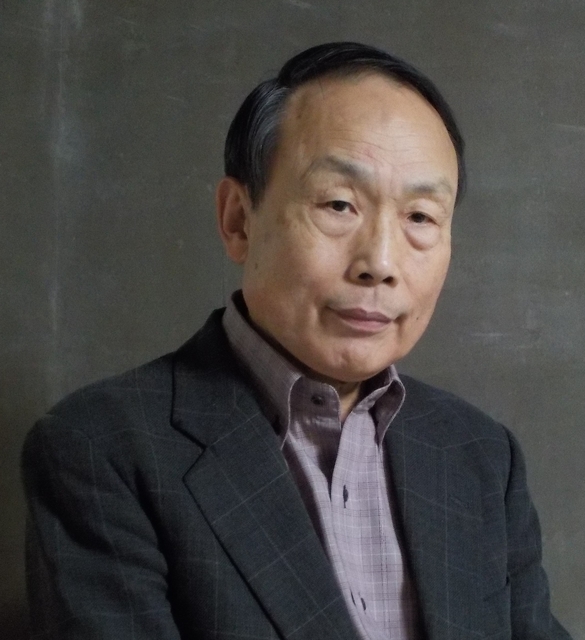貧困はいつの時代にもあるが、経済的困窮と心の貧しさは一体のものではない。(前述の通り)目指すものや自分のなすべきことのために<おでん種を売り歩いたり><質屋に住み込み奉公をしたりする>青年、彼らに理解を示し手を差し伸べる周囲の大人、そこには心の豊かさがあった。
なぜか。米軍による空襲・無差別攻撃によって焦土と化した国土。敗戦がもたらした<衣食住>という生きる基盤の確保に必死だった時代。「ゼロからのスタート」は国民全体が共有していた状況だった。だからこそ、「痛み」を分かち合い、希望を明日に託す思いが漲(みなぎ)っていたのだ。
敗戦から10年ほど経つと、朝鮮戦争による軍需景気をきっかけに経済復興期を迎え、ラジオに加えてテレビ放送が各家庭に浸透していった。やがて年末の国民的行事ともなった「NHK紅白歌合戦」が定着する。その年にヒットした流行歌が「紅組/白組」に分かれて熱唱されるのだが、この「檜舞台」に立つことが歌手たちにとってのステイタスであり、視聴者のファンにとってもテレビ画面にくぎ付けになる時間なのであった。

 時代は、中学生の集団就職や出稼ぎ労働者、跡継ぎになれない次男・三男などが地方から大都会へ流入し、孤独をかみしめていた頃だった。「望郷」「母への思い」「恋人への慕情」「都会暮らしの哀感」…作詞家・作曲家はそうした心情をすくい上げ、歌手もそれを自分の言葉として歌い上げた。つまり、スタッフ(レコード会社・プロデューサー・ディレクター/作詞家・作曲家)、出演者(歌手・バンド・司会者)、そして視聴者(興行の場合は、観客)が世の中に取り残される「痛み」を共有し共振していたといえる。
時代は、中学生の集団就職や出稼ぎ労働者、跡継ぎになれない次男・三男などが地方から大都会へ流入し、孤独をかみしめていた頃だった。「望郷」「母への思い」「恋人への慕情」「都会暮らしの哀感」…作詞家・作曲家はそうした心情をすくい上げ、歌手もそれを自分の言葉として歌い上げた。つまり、スタッフ(レコード会社・プロデューサー・ディレクター/作詞家・作曲家)、出演者(歌手・バンド・司会者)、そして視聴者(興行の場合は、観客)が世の中に取り残される「痛み」を共有し共振していたといえる。 昭和が終わり平成となり、そして、令和となった今、「NHK紅白歌合戦」の視聴率は激変している(80%⇒30%)。その社会的背景・時代と大衆音楽・制作態勢・カヴァー曲の問題・自分の「痛み」などについて考えてみたい。