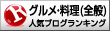現在、日本では様々な野菜を栽培していますが、農林水産省の統計で生産量等を把握しているものだけで約90品目にのぼります。 ですが、日本原産のものは、それほど多くはなく、私たちが普段食べている野菜のほとんどは、欧米や中国大陸から日本に持ち込まれたと言われています。日本原産の食用植物として、日本原産の植物は、日本列島の湿地帯に自然に生えていた雑草としての始まりました。日本原産としている野菜は20種類ほどという説が、日本では近年では主に約150種類の野菜を栽培、利用しているのですが、そのうちの日本原産の野菜は
1)独活(うど)、2)陸鹿尾菜(おかひじき)、3)牛蒡薊(ごぼうあざみ)、4)山椒、5)自然薯(じねんしょ)、6)ジュンサイ、7)芹(せり)、8)蓼(たで)、9)蔓菜(つるな)、10)白藍(はくらん)、11)浜防風、12)蕗(ふき)、13)菱(ひし)、14)松菜(まつな)、15)三つ葉、16)茗荷(みょうが)、17)百合、18)山葵(わさび)、19)ヤマゴボウ(有毒植物)などとしていますが、一方で日本原産の野菜は独活(うど)や、芹(せり)、三つ葉、蕗(ふき)、山葵、自然薯などほんの数えるほどとも言われます。
ヤマゴボウは、有毒植物として知られているのですが、葉・茎にはアルカロイドやサポニン、根には硝酸カリが含まれます。
そもそも原産とは、最初に産出した土地であり特に、動植物のもともとの産地といい最初に産出ということです。
大根や蕪、茗荷や葱などは古くから食べられていますが、海外から伝わったものとも考えられています。 牛蒡も古くに中国大陸から伝来としていますが、食用は主に日本で、他の国ではほとんど食用ではないようです。
◇大根は、春の七草に有り地中海沿岸または中央アジア原産で日本には、弥生時代までに中国から伝来で、江戸時代には各地で栽培するようになりました。
◇かぶも春の七草に原産地は、アフガニスタン周辺や地中海沿岸の南ヨーロッパ付近と考えられています。ヨーロッパでは紀元前からの栽培とのこと16世紀以降には食用と飼料用が広く栽培です。日本には中国を経由で弥生時代に渡来し、各地に多くの品種が存在し栽培が成立しています。記録的には「日本書紀(720年)」に記録としてあります。
◇和梨は日本原産と思われているのですが原産地は中国大陸で、古墳時代に大陸からの渡来人とともに日本に渡来したと考えられています。日本の野生種と交配し誕生した果実で、日本固有の栽培環境に適応して独自の進化を遂げているようです。奈良時代(710年~794年)以前に日本に伝来としています。
◇茗荷の原産地は東アジアで、日本を含むアジア東部の温暖地帯です。日本以外では台湾や韓国の一部にも生息を確認です。食用として栽培は日本だけで、香りの野菜として知られます。
◇葱の原産地は中国西部や中央アジア、シベリア、バイカル地方などと言われ紀元前200年ごろには中国で栽培を確認、土寄せの根深ネギの栽培方法も紀元前の中国で始まったといいます。日本には日本書紀(720年成立)の仁賢天皇6年(493年)9月に「秋葱」の名で登場するのが日本最古の記録があり奈良時代(710年~794年)以前から伝来し、江戸時代には全国で栽培としています。
◇ハクラン(白蘭)は、昭和34年、当時平塚市にあった農業技術研究所でハクサイとキャベツの種間雑種で、バイオテクノロジーによって開発の日本初のバイオ野菜です。昭和34年に平塚市の農業技術研究所で両者は染色体数が異なり、自然状態では交雑できない交雑植物の誕生でした。
◇浜防風は東アジアの台湾、中国、朝鮮及びロシアの海岸からカムチャッカに広く分布し、日本も原産国のひとつとしています。
◇蕗(ふき)は、北海道から沖縄まで野生種が分布しているほか、日本以外にも中国や韓国でも自生しているようです。
◇菱(ひし)は、日本全国の平地にある池や沼、湖などに多く群生し、朝鮮半島や中国、台湾、ロシアのウスリー川沿岸地域などにも分布しています。
14)松菜(まつな)は、ヒユ科の一年草で、海岸の砂地に生える植物です。若芽は食用にでき、野菜として栽培することもあります。
◇茗荷(みょうが)は、日本を含むアジア東部を原産として 3世紀末に書かれた「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」にもその名が見られるなど、古くから全国に自生しています。
◇百合は、日本原産の植物として、日本には15種類ほどが自生し7種類は日本特産種で、ユリを食用に品種改良の「ゆり根」という野菜は、江戸時代ごろから食用としていたようです。オニユリやヤマユリの球根で収穫までに約3年といいます。北半球で発見の植物で野生種では、アジア、ヨーロッパやアメリカに南は赤道付近やインドでも発見しています。
◇山葵(わさび)は、日本原産。中国大陸の近縁種とは、約500万年前に分化したと推定しています。
◇マルミノヤマゴボウは、本種は有毒です。「山ごぼう」の名で漬物として売られているは、モリアザミの根です。
◇大豆の原産地は中国東北部、黒龍江沿岸と一般的に考えられています。紀元前2838年に中国を支配した神農皇帝の医薬の書物『神農本草経』に大豆に関する記録が見られ、古くは4000年前から栽培と推定です。大豆の原産地は中国東北部、黒龍江沿岸と一般的に考えられています。大豆の原種はツルマメ(ノマメ)として、日本には中国から朝鮮半島を経て伝来としており、縄文時代中期に痕跡が見られ栽培が始まったようです。
全国的に流通し、特に消費量が多い国内生産量が多い野菜を例として見てみますと、だいこん、さといも、ねぎ、きゅうり、なすの5品目は縄文から平安時代にかけて渡来と見られ、ばれいしょ、キャベツ、ほうれんそう、トマトの4品目は江戸時代に、にんじん(西洋種)、はくさい、レタス(結球種)、たまねぎ、ピーマンの5品目は明治時代以降に日本に伝わったと言われています。
外国人が苦手な日本の食材としているのは、生卵 、刺身、板海苔は、海外ではもともと食べる習慣がないようです。
農林水産省の統計によると、家計消費用の野菜は国産割合がほぼ100%であるのに対し、加工・業務用の野菜は国産割合が約7割となっています。
輸入量が多い野菜は、生鮮品では、たまねぎ、🥕にんじん、かぼちゃが多く、たまねぎが全体の3割強を占めます。🧅玉葱、🥕人参は、加工原料用や業務用で多く使われています。その他、加工品として、🍅トマト(ピューレ、ジュース等)、🌽スイートコーン(冷凍、缶詰)、🥕人参(ジュース)類を輸入しています。野菜の自給率向上に向けて、令和2年(2020年)3月に定めた食料・農業・農村基本計画では、需要が拡大する加工・業務用野菜について輸入品から国産品への置き換えを目指すこととしています。
日本原産の野菜といわれているものの多くは、有史・文字の伝来以前、縄文時代の貝塚からの痕跡のある物、海外で自生の環境が同程度であるなどで、原産地が決められているように思えました。そして、その後に、日本には導入以前には、見られていなかった野菜類に、多く見られる地域が原産地表示として見られているのではないのかと私の考えているところです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。