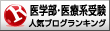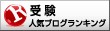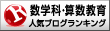中学受験ではもちろん合格本願で勉強を継続していくわけだが、その勉強のやり方も考えてほしいとは思っている。どんな方法でも合格は合格なのだが、拙いやり方でやっていくと先々詰んでしまうこともある。
東海地区は関東関西地区ほど塾の種類がないので、私は算数の答案をみればどこの塾に通っているのかは分かってしまう。ちょっとした立式の違いが塾の指導方法を表しているからだ。
正解できていても、やり方に不安を感じることはある。妙に公式化された解答には不安を憶える。意味が分かって解答しているかが疑問だから。
といっても、実は上位層と呼ばれるgiftedには塾も形式も関係ない。どんな教え方をされても本質が捉えられるから。入学した後の学校の方針もあまり関係ない。自分で咀嚼できるのだから、塾や学校は単なるペースメーカーでしかないのだ。
これまで何人かのgiftedにあったが、彼等彼女等が一様に言うことは"中学受験は楽しかった"
塾は興味付けの場として機能しているので、役に立っていないわけではない。しかし、形式形態には拘らない。
逆に中位層以下は、塾や学校の方向性に左右されてしまう要素が多い。
大学受験でも生徒によって私は学習方針を変えている。
上位層には”数学なんて暗記すればいいから”と言いながら、どんどん演習を上げていく。自己消化力が高いのだから、どんどん食べさせた方がいい。刺激的な試みを継続した方がレベルアップに繋がるし、楽しいだろうし。
中位層には、問題を増やし過ぎないようにして、よく考えさせることにしている。解法は暗記するものではなく、問題解決の道具であることをしっかりと認識させる。
下位層には、また逆に暗記数学を推進している。数学が解ける楽しさを植え付けるためだ。数学を友達にしたあとで、その後の戦略を考える。
中学受験での上位層は、解法を憶えているようなフリをして、実は覚えているわけではない。解法を覚えるなんて"しちめんどくさい"ことをするわけがない。物凄い速さで状況把握をして、適切な解決手段を弾き出す。傍から見ると、解法を暗記していたように思えるのだが。
つまり、上位層のマネをすれば成績が上位になれるのではないかという考え方は、全くうまくはいかない。
自分の子供が凡人であれば、どんな塾に入れて、どんな方法を取って、どんな学校に入れるのかは、熟慮を重ねないといけない。
giftedならば、適当に一番近い塾に入れておくのがよいだろうよ。
いくた