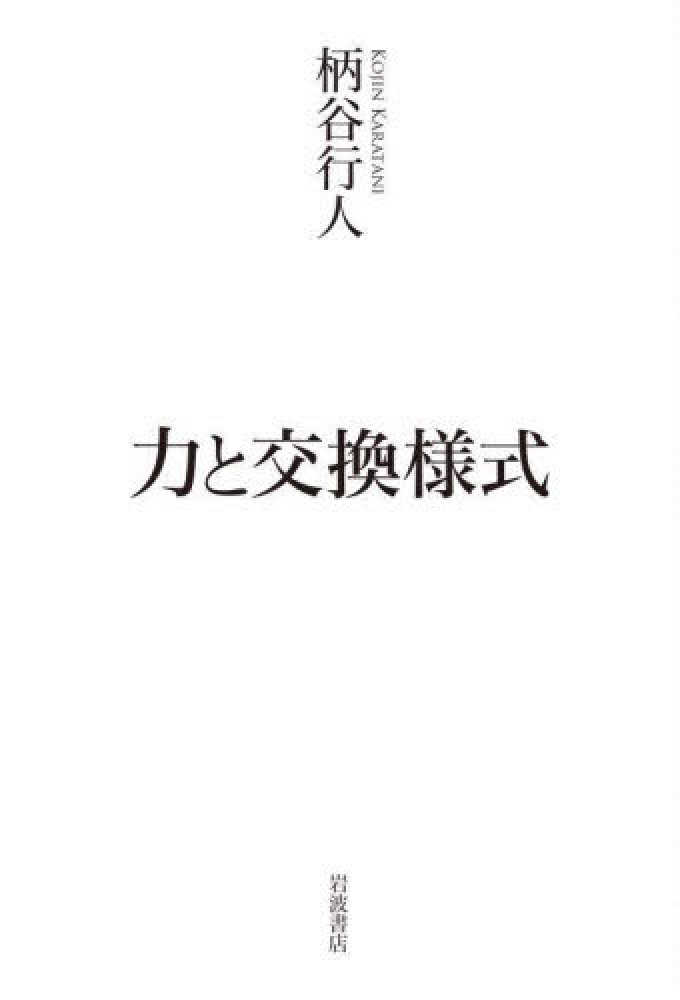「黙示録」の4色の馬〔ヨハネ黙6:1-8〕
【7】 エンゲルス――『原始キリスト教史によせて』
エンゲルスは、亡くなる前年に『原始キリスト教史によせて』という論文を書いています。エンゲルスの原始キリスト教史論は、この論文に集中的に書かれています。柄谷氏による紹介は十分ではないので、まず内容をかいつまんで述べておきたいと思います:
『原始キリスト教史によせて』《あらすじ》
かつてブルーノ・バウアーは、キリスト教のなかにある純ギリシャ的要素・ギリシャ=ローマ的要素を検出することに努めました。これらの要素は、ユダヤ人の原始キリスト教団の宗教が、ローマ帝国に拡がり、「世界宗教」となる過程で変質していったことを証明しているからです。バウアーは、キリスト教が「すくなくともその世界宗教的形態においては、ローマ=ギリシャ的世界のまったく独自の産物である、という証明の基礎を築いた。」バウアーにかかると、「イエスおよび彼の信徒たちにかんする新約聖書の物語」は、歴史的根拠の無い空想となってしまい、初期教団の内部状況と感情闘争が、架空の人物のうえに移し換えられた伝説が『新約』だ、ということになってしまう。その現場は、じつはガリラヤでもエルサレムでもなく、3世紀後半以後のローマなのである、とバウアーは主張した。(『原始キリスト教史によせて』, in:『マルエン全集』第22巻,p.452.)
しかし、エンゲルスの考えるところでは、『新約聖書』の中で「ヨハネの黙示録」だけは、紀元67-68年に書かれた真正文書である〔現在では、69年成立説と 96年成立説がある――ギトン註〕。「原始キリスト教の実体を確定するためには、この書は〔…〕重要なものである。」「この書のキリスト教が、実際の純正の原始キリスト教である」。その教義内容は、325年ニケーア公会議で確定されたローマ帝国の正統キリスト教とは大きく異なっていた。①「三位一体説」は存在しないばかりでなく不可能だった。②「原罪」の教義は「何のあとかたも見出されない。」③「洗礼」も「聖餐」も無かった。④著者ヨハネとその信仰仲間は自分たちをユダヤ人と意識しており、ユダヤ人の教団だった。
⑤しかし、彼らは異教徒への布教をめざしており、「ヨハネ黙示録」には、「原始キリスト教が世界宗教に発展することを可能にした根本観念」が見出される。それは、「キリストの贖罪」という教義で、フィロン学派〔紀元前後のアレクサンドリア。ユダヤ教をギリシャ哲学で解釈した。〕から借りてきた観念だった。当時のセム族・印欧語族には、「人間の行為によって感情を害された神々は、犠牲 いけにえ によって宥 なだ めることができる」という観念がありました。「犠牲」にかかわるさまざまな儀式は、「信仰を異にする者たちとの交際を困難にしたり禁止」するためのものだったが、「世界宗教」が成立するためには、この垣根を取り払う必要があった。そこで、……:
『フィロン学派から借りてきた根本観念は、一人の仲介者〔イエス・キリスト――ギトン註〕の大きな、自由意志による犠牲のおかげで〔…〕あらゆる時代および人間の罪が終局的に償 つぐな われるという考え方であった。このことでもって、これ以上の犠牲はいっさい不必要となり、それとともに、多数の宗教的儀式の基礎は失われてしまった。〔…〕儀式を自由』にすることが、『世界宗教の第1条件だったのである。』
エンゲルス『原始キリスト教史によせて』, in:『マルクス・エンゲルス全集』第22巻,1971,大月書店,p.455.
ミケランジェロ『聖家族』部分。
原始キリスト教には、「後代のキリスト教の教義も倫理も存在しない。それに代わるものは、全世界を向こうに回した闘争〔…〕に勝ち抜くであろう、という感情である。それは、今日のキリスト教徒」からはすっかり失われているが、現代社会の他の極である「社会主義者たちのもとにのみ見出せる闘争慾と必勝感とである。」
「世界との闘争と、これと同時に行なわれた改革者同士間の闘争とは、原始キリスト教徒にも社会主義者にも共通」して見られる。「それは大衆運動である。そして大衆運動というものは、はじめのうちはどうしても混乱する。〔…〕混乱は多数の宗派の形成となって現れる。」それら宗派は、「共通の外敵に対するのと〔…〕同じ程度の激しさ」で、互いに争いあう。「黙示録」の著者ヨハネも、「広い・罪深い外部世界に対するのと同じ非妥協的な激しさ」で諸宗派を攻撃しています。
「最初期のキリスト教は、どんな種類の人びとから徴募されていたか? 主として[労する者と重荷を負う者]〔マタイ11:28〕つまり、革命的要素に向くような、最下級の人民」のなかからである。「都市では、落ちぶれた自由民」、奴隷、解放奴隷。ローマ帝国属領のラティフンディウム(大農場)と農村では、奴隷、債務奴隷に転落しつつある小農民。これらさまざまな信徒すべてを一挙に解放するような「共通の道は、絶対に存在しなかった。」「落ちぶれた自由民にとっては、」先祖が自由市民であった都市国家ポリス。奴隷にとっては、ローマに征服される以前の故郷の世界。「小農民にとっては、滅ぼされた氏族社会」――を回復してそこに戻ることこそが、救済だった。つまり、信徒たちが望む “救い” の世界は、ばらばらだった。(pp.456-457,460.)
「古代が到達した」最先端の「社会群は、部族であり、そして血縁諸部族の同盟であった。」ギリシャとイタリアのポリスも、「いくつかの血縁部族」を包括した組織であり、国民からなるような、あるいは国民を支配するような国家ではなかった。しかし、ローマの世界支配は、氏族・部族の「小規模な結合を一挙に終わらせた。軍事力、ローマ式の裁判権、徴税機構は、」伝統的な氏族・部族組織をすっかり解消した。氏族・部族の「独立性と独自組織を失わせたのは、文武当局による強権的な掠奪であった。」
「ローマの巨大な世界権力」の前では、小部族・小都市の個々の反抗は絶望的だった。奴隷化され、抑圧され、窮乏化され、しかも互いに分断され対立している「諸種の人間群のすべてに共通する出口」が見出されねばならなかった。「単一の大きな革命運動が、彼らすべてを包容しなければならなかった。」
「出口は見つけられた」が、「この世においてではなかった。」そのような普遍的な解放は、「宗教面の出口」しかありえなかったからだ。「そこに一つの別の世界が開けた。」もともと古代人のあいだでは、肉体の死を越えて霊魂が生き続けるという考えは、徐々にしか広がらなかった。ギリシャ人も、死後の生などはありえないと思っていた。「そこへキリスト教がやってきて、来世における褒章と懲罰を本気で考え」させ、「天国と地獄をつくりだした。」
ところで、私たちのふつうの常識的な思考では、「現世・この世」と「来世・あの世・彼岸」は、まったく別のものだと思われています。「革命運動」とか「世のため」だとか「メシアの救済」だとかは「この世」で行なわれることで、「天国」「極楽」は「彼岸」にあるものだと思われています。「地上に神の国を創る」「地上を仏国土とする」などというのは、「この世」にやってきたキリストや仏が、「この世」で行なう事業だと私たちは考えます。
しかし、この論文でエンゲルスが考えている枠組み、また彼が「ヨハネ黙示録」に見出す考え方は、(私の受ける感じでは)少し違うようなのです。それを図示すると、↓次のようになります。
この世(ローマ帝国,近代,現代)
// 千年王国,神の国 天国(地獄)
つまり、決定的な断絶は、地上に建設される「千年王国,神の国」と天上の「天国(Paradies)」のあいだにではなく、「この世」と、「千年王国,神の国」すなわち理想的な地上世界とのあいだにあるのです。
キリストの再臨。 © triangulations.wordpress.com
「ヨハネの黙示録」は、キリストと神の「審判」によってもたらされる「千年王国,神の国」を、「天国」と区別していません。むしろ、信者のための「天国」は、地上にこれから建設される・その「千年王国,神の国」のほかには存在しないのです。人が個別に死んで「天国」に迎えられるというような話は、ここにはありません。「この天上の楽園は、〔…〕信徒のために、死と同時にすぐさま開かれるものではない。新しいエルサレムを首都とする神の国は、地獄の諸勢力との激しい戦いのあとで初めて獲得される」。その「戦いは、最初期のキリスト教徒の考えでは、まぢかに迫っているものであった。」(pp.460-461.)
この、いま「まぢかに迫った戦い」のあとで、キリストは地上に「千年王国」を築き、戦いで倒れた殉教者たちが蘇 よみがえ って、キリストとともに、この理想世界を指導する。だから、聖徒たちが死をも恐れずに圧政と迫害に抗して戦うのは、「天国」への昇天が約束されているからではなく、彼らの戦いによって地上に「千年王国」が築かれ、不当な死から復活してそこに迎えられるからなのです。
『まずヨハネが見るのは、7つの封印で封じられた1冊の巻物を手にして御座の上にいます神と、その前方にいる〔…〕羔羊 こひつじ(キリスト)〔自ら犠牲となって人類の罪をあがなった――ギトン註〕である。封印が解かれる際にあらゆる種類の奇跡が生じる。〔ギトン註――神が第1~4の封印を解くと4色の馬が躍り出る(↑トップ画参照)〕第5の封印が解かれ〔…〕ヨハネが神の祭壇の下に見るのは、〔…〕キリストの殉教者たちの霊魂である。彼らは大声で叫んだ。主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、〔…〕私たちの血の報復をなさらないのですか? すると、〔…〕もうしばらくのあいだ待つように、もっとたくさんの殉教者たちが殺されねばならぬ、と』の神の言葉で『宥 なだ められる。
――こんなわけで、ここ〔原始キリスト教――ギトン註〕ではまだ、汝の敵を愛せよとか、汝を呪う者を祝福せよ、などという「愛の宗教」については、ひとことも語られていないのである。ここで説かれているのは、おおっぴらな報復、キリスト教徒迫害者に対する〔…〕正々堂々たる報復である。〔…〕危機が近づけば近づくほど、禍害と罰とが天からますます繁く降ってくればくるほど、ますます大きな喜びをもって、わがヨハネは告げ知らせる。いわく、おおぜいの人間はなお相変わらず己が罪を悔い改めようとしない。いわく、神の新たな鞭がまだまだ彼らの上にびゅんびゅんと降ってこなければならない。〔…〕この王〔皇帝ネロ――ギトン註〕は、42ヵ月間〔…〕地上を支配し、信徒たちを死に至るまで迫害して、不信心をはびこらせるであろう。しかしそのあとに大決戦が起こり、聖徒と殉教者たちは、大淫婦バビロン〔帝都ローマを指す――ギトン註〕の滅亡と、そのあらゆる追随者たち、すなわちおおぜいの人間の滅亡〔…〕によって、仇を討ってもらうであろう。
悪魔は底知れぬ所に突き落とされ、そこに 1000年のあいだ閉じ込められる。その期間、キリストは、死から復活した殉教者たちとともに、その王国〔千年王国――ギトン註〕を指導する。〔もちろん、こんな「D」の世界を「指導」できるのはキリストだからであって、生身の人間はどんな天才でも偉人でも「D」を計画も指導もできない。――ギトン註〕
しかし 1000年後に悪魔はふたたび解き放たれる。そして新たに霊界の大戦闘が起』き、『悪魔は終局的に打ち負かされる。〔…〕第2の復活が行なわれ、残りの死人たちもまた蘇り、神の審判の庭に現れる。こうして、信じる者は、新しい天と新しい地、新しいエルサレムへ入って、永遠の生活を送ることになる。〔…〕この都で神は僕 しもべ たちのあいだに住まい、太陽に代わって彼らを照らす。もはや死もなく、悩みもなく、苦しみもない。〔…〕
Apocalypse (fresco) , Osogovo Monastery, North Macedonia © Wikimedia.
三位一体に関しては何の痕跡もない。〔…〕原罪ならびに信仰による無罪の立証に関する教義についても、わが黙示録は〔…〕知るところがない。この好戦的な最初期教団の信仰は、後代の・勝利の座についた教会のそれとは、まったく別種のものである。羔羊の贖罪の犠牲とならんで、キリストのまぢかい再来と、すぐにも始まる千年王国とが、その信仰の主要内容である。〔…〕
世界宗教の萌芽はそこ〔ヨハネ黙示録――ギトン註〕にある。しかしその萌芽はまだ数千の発展可能性を無差別に包含しており、そういう可能性が現実化して後年の無数の宗派の形をとったのである。』
『新約聖書』のうち「ヨハネ黙示録」以外の『後年のものはすべて、西方的なギリシャ=ローマ的な水増し作である。一神的ユダヤ宗教〔原始キリスト教――ギトン註〕の媒介によってのみ、後期ギリシャ俗流哲学の洗練された一神論は、宗教の体裁をとることができ、この形でのみ、それは大衆をつかむことができたのである。しかし、いったんこの媒介が見つけ出された後では、それ〔原始キリスト教――ギトン註〕は、ギリシャ=ローマ世界においてのみ、そしてこの世界を通じて獲得された思考材料の上で発展しそれと融合することによってのみ、世界宗教となることができたのである。』
エンゲルス『原始キリスト教史によせて』, in:『マルエン全集』第22巻,pp.462-463,467-470.
《あらすじ》――終り
もともとギリシャ哲学は、ギリシャの多神教のもとで誕生したのですが、ヘレニズム~ローマ時代になると、一神教的傾向を強めていきます。アレクサンドリアのフィロン哲学や、プロティノスらの新プラトン主義哲学が、その例です。しかし、哲学という形態では、なかなか大衆にまでは広がっていかなかったのも事実です。この状況を変えたのが、原始キリスト教との結合でした。
逆に、原始キリスト教のほうからいえば、「キリストの贖罪」という・世界宗教となりうる萌芽的要素はもっていたものの、じっさいに他の宗教・宗派を抑えてローマ世界に拡がり「世界宗教」となるには、一神的後期ギリシャ哲学との結合を通じて、ギリシャ=ローマ的西方思想を取り入れ、本来の原始キリスト教団とは懸け離れたものとなることが必須の階梯であったのです。
【8】 「千年王国」の革命、「氏族社会」の自由と自立
――晩年のマルクス/エンゲルス
このようにエンゲルスによってまとめられた「ヨハネの黙示録」の内容は、ミュンツァーの「革命神学」にも通ずるもので、「交換様式D」からくる思想の特徴を備えています。(私見ですが、私は仏教の弥勒信仰、とくに「弥勒上生信仰」には「D」の痕跡があると見ています。)
エンゲルスは、《オリエント全体に、〔…〕うようよして〔…〕生存闘争》を繰り広げていた星のような新興教団のなかで、「原始キリスト教」が世界宗教となりえたのは、「一切の民族宗教と〔…〕儀礼とを拒否して、差別することなくすべての民族にうったえ」ることができたからだ、と云います。つまり、原始キリスト教には、「交換様式D」からくる普遍的要素があった。
しかし、キリスト教は、その後の布教の過程で、ギリシャ=ローマ的要素を大いに取り入れて換骨奪胎し、その過程で、「原始キリスト教団」のもっていた「交換様式D」からくる要素は、「黙示録」に痕跡を残して消えてしまった。だから、ローマ《帝国》(交換様式B)の国教となることができたのです。キリスト教は、《その世界宗教的形態においては、ローマ=ギリシャ的世界のまったく独自の産物である。》
Les Bryant.
『原始キリスト教の歴史は、近代の労働運動との注目すべき接点を提示する。後者と同じく、キリスト教は発生時には、被圧迫者の運動であった。それが最初に現れたのは、奴隷および解放奴隷の、貧者および無権利者の、ローマに征服または撃破された民衆の宗教としてであった。両者は、キリスト教も労働者社会主義も、隷従と困窮からの・到来まぢかい救済を説く。〔…〕
両者とも迫害・追及され、その信奉者は排撃されて、例外法のもとにおかれる。一方は人類の敵として、他方は帝国の敵、宗教・家族・社会秩序の敵として。
ところが、あらゆる迫害にもかかわらず、いや、迫害によって直接促進されさえして、両者とも勝ち誇って、たえまなく前進する。キリスト教はその成立後 300年にしてローマ世界帝国の公認の国教であり、社会主義は 60年になるやならずで、勝利の絶対確実な地位を獲得した。〔「原始キリスト教史によせて」,1894年, in:『マルエン全集』第22巻,大月書店,p.452.〕
この文で一つ気になるのは、「社会主義は 60年になるやならずで、勝利の絶対確実な地位を獲得した」という条である。〔「勝利宣言」として読んでしまいそうになるが、エンゲルスの本心は、むしろ逆だ。――ギトン註〕〔…〕社会主義がこのとき、国家公認の宗教、すなわち「国教」となることを意味するのではないか。
〔…〕イギリスでは 1900年に労働者代表委員会〔労働党の前身――ギトン註〕が結成されたが、それが唱える社会主義は国家公認のものであり、マルクスやエンゲルスが考えた社会主義革命とは程遠いものであった。また、ドイツでは社会民主党は 1890年代初め』に合法化されたが、『合法化とともに「国教」となったといってよい。
つまり、1848年革命以後、社会主義は資本主義国家にとって危険なものではなくて、むしろ必要な一要素となったのだ。〔…〕
ドイツにおいて、エンゲルスの遺志を受け継ごうとしたのは、〔…〕カウツキーだけであった。〔…〕それは、いわゆる “マルクス主義者” にはあまり知られていない領域にかかわるものであった。〔…〕たとえば、『トマス・モアと友人』『キリスト教の起源――歴史的研究』や『中世の共産主義』のような大部の著作に示されている。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.369-371.
そのカウツキーは、「ロシア十月革命」〔1917年「二月革命」後の混乱を利用してレーニンらが政権を横取りしたクーデター〕を批判して、レーニンから「背教者」として糾弾されました。ソ連崩壊後、レーニンは彼に続くスターリンとともに、ようやく左翼圏でも批判を浴びるに至っていますが、カウツキーは復権されないままです。カウツキーとともに、「社会主義の科学」に先鞭をつけたエンゲルスの “隠れた功績” もまた、忘れ去られたままなのです。
晩年のマルクスは、「古代社会」へ関心を向け、エンゲルスは「原始キリスト教」へと向かった。しかし、……
『交換様式の観点から見ると、彼らが同じ問題、すなわち、資本と国家を揚棄した共産主義社会の可能性を追求していたことがわかる。〔…〕マルクスは『古代社会』、すなわち交換様式Aが優位にあった社会を考察し、共産主義を、そこにあったものの “高次元での回復” として見るに至った。
一方、エンゲルスは未来の共産主義を、原始キリスト教にあった “何か” を回復するものとして見た。これも、彼自身が唱えた史的唯物論〔…〕「科学的社会主義」とは異質な観点であった。このときエンゲルスは共産主義を、生産様式からではなく、事実上交換様式から見ていたのである。すなわち、交換様式Dの再現として。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.372.
マルクス/エンゲルスの死後、彼らが遺した理論的可能性を読み取ろうとした人たちは、カウツキー以外にも、いることはいました。ただし、政治運動圏のはるか外部に。。。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!