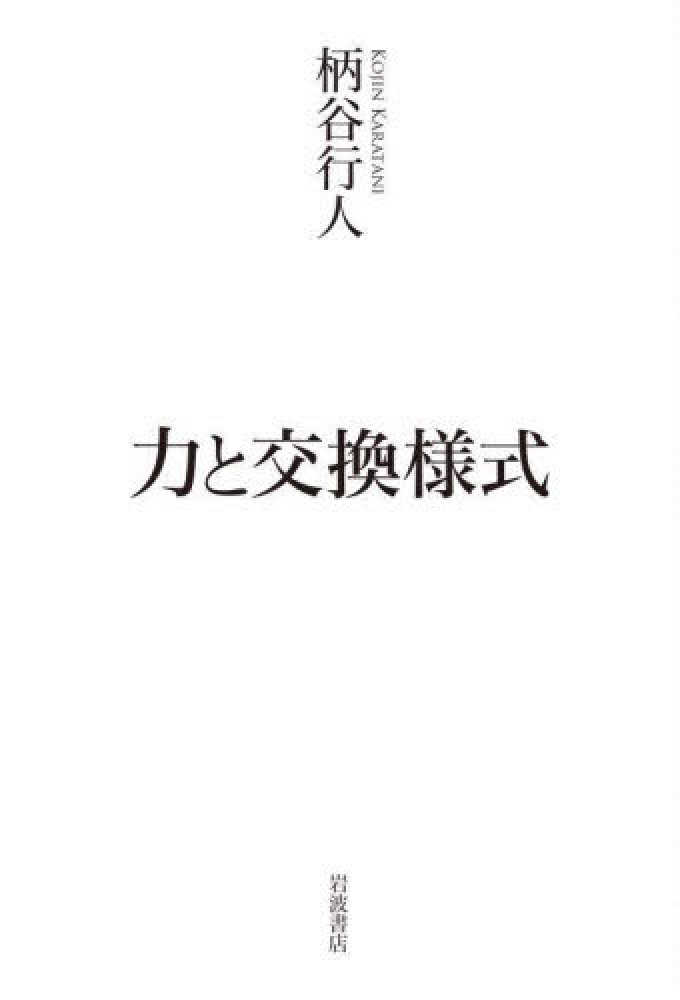大西洋中央海嶺の熱水噴出孔: 地球生命の誕生地として有力視されている。
a hydrothermal-vent in 2,980 meters of water
on the Mid-Atlantic Ridge ©MARUM/Wikimedia Commons
【27】 ベンヤミン,ブロッホと、柄谷氏
『ベンヤミンの場合、神話的暴力が force であり、神的暴力は violence である。彼はいう。神話的暴力からの解放は、神的暴力なしにはありない。そうすると、国家や資本は「神話的暴力」であり、共産主義は「神的暴力」である、ということになる。
このような区別は謎めいて見える。〔…〕このような謎は解ける、と私が思ったのは、“交換” から観念的な “力” が生じるということ、ゆえにまた、“交換” が異なれば、異なる “力” が生じるということに気づいたときである。
〔…〕たとえば、服従することと保護することが交換される時に国家権力が成立する。それは交換様式Bから生じる観念的な力である。〔…〕ベンヤミンに関していえば、彼がいう force とは交換様式Bから生じる力であり、violence は交換様式Dから生じる力である。
ブロッホがいう “希望” についても同様のことがいえる。“希望” とは「中断され、おしとどめられている未来の道」であり、それを「反復」させるのが交換様式Dから生じる力にほかならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.384-385.
前回までにベンヤミンを詳しく検討してきた後で、柄谷さんによるまとめ↑を改めて読むと、いくつか気になる点が出てきます。
まず目立つのは、“force” “violence” という用語です。これらは、ソレルの主張した暴力概念であって、ベンヤミンの言う「神話的暴力」と「神的な暴力」にそのままイコールであるわけではありません。ソレルのサンディカリズムは、被治者の “violence”、つまり労働者の一斉ストライキによって資本主義国家機構を機能できなくすることで社会を変革すると主張しています(つまり、「働かない」という消極的暴力)。しかし、ベンヤミンの言う「神的な暴力」は、イスラエルの会衆に加えられた神罰が例に挙げられていたように、かならずしも、被治者から治者に向かう反抗的なものではないのです。
ベンヤミンの「神的な暴力」は、恣意的な「神話性」に基づく不正義・を免れない「法的暴力装置」に対して、「衝撃」を与え、「脱措定」する力として提起、ないし定義されたものです。したがって、それがどこから来るかは問わないのです。
また、ソレルは、国家の法的機構を破壊して機能不全にすることしか主張しません。その後にどんな国家にするのか? 国家を廃止するというなら、どんな社会を作るのか? その点をまったく考えていないのです(つまり、アナーキズム)。しかし、ベンヤミンの場合には、「法」を「脱措定」する、つまり、既存の「法」を破壊した後で、そこから「正義」を生成させ、より「正義」にかなう形に「法」を「救出」する(再生させる)という展望があるのです。
そうすると、「国家や資本は[神話的暴力]であり、共産主義は[神的暴力]である」という柄谷氏のまとめは、そのまま受けいれるわけにはいかなくなります。
バリケードを設けて鎮圧軍を銃撃する「スパルタクス団」。1919年1月12日
さらに大きな問題は、ベンヤミンの言う「暴力」と、柄谷氏の「交換様式から生じる観念的な力」は、かなり異なったものではないか? 少なくとも、両者の見方は大きく異なるのではないか? ――という点です。
ベンヤミンの言う「暴力」とは、文字通り、物理的な有形力の行使であって、現実的なものです。そのことを明確に見てとれるのは、「神話的暴力」やその発展形態である国家の「法的暴力」の場合でしょう。もっとも、国家の暴力装置といえども、常に発動状態にあるわけではなく、日常的には、脅迫ないし威嚇によって機能を果たしています。それにしても、反抗や違反があれば何時でも発動される・という保証があればこそ、威嚇は効果をもつのです。その意味で、ベンヤミンの言う「暴力」とは、物理力の行使だと言ってよい。
「神的な暴力」の場合は、どうでしょうか? ベンヤミンは、「神的暴力」は「神話的暴力」とは異なって、脅迫的ではないが「衝撃的」であり、「無血的」だが「致命的」だと特徴づけています。たしかに、『民数記』の神罰にしろ、自然災害にしろ、「無血」ではすまない災いです。しかし、理想的意味では、「無血」であってこそ純然たる「神的な暴力」と言える。人間の肉体的生命に「血なまぐさい破壊」を加えることなく、「致命的衝撃」によって神話的拘束を解体し、「生き生きと生きる生命」を活性化させるのが「神的暴力」である。 ベンヤミンは、そう考えていたように思われます。
なるほど、「無血」という点では、ソレルの主張するゼネストも「無血」にはちがいなく、「神的暴力」として有効でありうるのかもしれない。そこまではベンヤミンも認めます。しかし、ゼネストによって国家と「法」を破壊した後で、ソレルの「暴力」は何をするのか? そこまで考えなければ、「法」を脱措定し「正義」を救出する「神的暴力」とは認められない。そこまでの射程を持たないものは、「革命的暴力」などとは言えない。ベンヤミンは、『暴力批判論』の結論部分で、そう語っていました。
このように、ベンヤミンの言う「暴力」は、どこまでも現実的な物理力、衝撃力の行使にかかわっていました。
これに対して、柄谷氏が着目する「交換様式から生じる力」とは、あくまでも「観念的な力」なのです。たとえば、「交換様式B」で、国家というものは、実際には支配の手段として「法的暴力装置」を必ず具えているはずです。しかし、柄谷氏は、そこには注目しないのです。むしろ、暴力的な支配というものは決して長続きするものではない、という条理を前面に出し、「服従」と「保護」の「交換」によって被治者がみずから進んで治者に服従する面を重視します。
聖武天皇(NHKドラマ)
これは、かならずしも非現実的な見方ではないと思います。ある意味で卓見かもしれません。というのは、歴史上に現実に、国家の「法的」暴力装置をみずから破壊する帝王というものも存在したからです。にもかかわらず、そのことによって国家の支配は微動だにしなかった。たとえば、日本史では、聖武天皇が、そのような帝王でした。聖武は、牢獄にいる罪人をひとり残らず無差別に釈放してしまう、ということを何度か行なっています。その反面で、貴族の反抗――藤原広嗣の乱など――に対しては容赦なく武力を差し向けて撃滅しています。ちょっと批判しただけなのに、「謀叛」と決めつけて弾圧する。だから相手は本当に反乱せざるを得なくなる。ほとんど、天皇のほうから反乱を作り出しているようなものです。(⇒:【聖武と行基集団】(28))
この一見すると乱脈に思える統治も、「交換様式」の観点で見ると、意外に合理的であることがわかります。
つまり、聖武は、「服従と保護」という「交換」関係については神経質なほど厳格で、この交換に反する「反抗」は、どんな微小な芽も見逃さずに摘みとる。それゆえに彼の支配は盤石 ばんじゃく だったのです。
もっとも、柄谷氏のこの「交換様式B」という見方にも疑問はあります。たとえば、柄谷氏の言う「交換様式C」〔商品交換,商品経済〕のほうは、もっぱら物質的な交換の関係だけを見ています。資本主義社会には、さまざまな非物質的な水平的 “交換” が見られるのに、それらはすべて捨象されています。ところが、「交換様式B」になると、逆に物質的な関係が捨象されて、「服従と保護」という非物質的な “交換” だけが俎上に載せられているように見えるのです。古代国家の「租庸調」「班田収授」などの垂直的物質 “交換” はもちろん、中世国家でも西欧近世の絶対主義国家でも、貢税の収奪を中心とする物質的関係は、国家の存立に必須の柱だった。しかし、それらには眼が向けられていないように見えます。
【28】 ジーグムント・フロイト
――「タヒの欲動」とは何か?
さて、柄谷氏は、ベンヤミンの「神的暴力」、ブロッホの「希望」を足がかりにして「交換様式D」の解明に進もうとするのですが、そこへ移る前にフロイトの精神分析学を援用します。ブロッホは、フロイトの「無意識」概念を念頭に置いて、「未だ意識されないもの」「未意識」の概念を立てています。ブロッホによれば、…
『この「未意識」こそ、「未来の道」としての社会主義をもたらす〔…〕。つまり、共産主義は、人が理想化する〔理想と思う――ギトン註〕社会を意識的に実現することではない。それは、いわば「〔ギトン註――太古の時代に〕中断され、おしとどめられている未来の道」が、おのずと回復されることだ。つまり、未意識とは「反復」にほかならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.386.
フロイトの精神分析といえば、よく知られているのは、前期フロイトの「快感原則」です。しかし、柄谷氏がここで注目するのは、「快感原則」ではなく、第1次大戦による外傷性神経症の治療をきっかけに再考し変化した・後期フロイトの、「タヒの欲動」を中心とする深層心理学なのです。
人間の「心的過程は、不快を避け、快を生むような結末に向って進む」という「快感原則」は、一般社会の常識と一致しているのでわかりやすい。これに反して、後期フロイトが唱えた「タヒの欲動」というのはたいへん解りにくいのです。
そこで、以下では、まずフロイトの著述にさかのぼって、この「タヒの欲動」をめぐる思考をたどっておきたいと思います。
『本能とは、生命ある有機体に内在する衝迫であって、以前のある状態を回復しようとするものであろう。以前の状態とは、生物が外的な妨害力の影響のもとで、放棄せざるをえなかったものである。また、本能とは、一種の有機的な弾性であり、あるいは有機的生命における惰性の表明であるとも言えよう。』
フロイト,小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,新装版第6巻,2023,人文書院,pp.176-177.
たとえば、うつわに水を入れて、外部から力を加えて揺らすと、うつわの水は揺れるが、しばらくすると揺れは小さくなって、もとの静止水面に戻ります。
このような無機物質の “原状回復” の性質が、生命体にも備わっている。生命体には、固有の「衝迫」として、もとの状態に戻ろうとする性質が内在している。それが、「本能」というものの起源、ないし最も基礎的な本質だと、フロイトは言うのです。
だとすると、そのような性質が、無機物質から有機物質(生命体)に受け継がれたのは、地球上に生命が誕生した時であったはずです。したがって、その時に、誕生したばかりの生命体が持っていた「衝迫」とは、もとの無機物質に戻ろうとする「衝迫」、すなわち、生命の側のコトバで言えば、「タヒのうとする衝迫/本能」であったことになります。
生物には、「発展する能力」だとか「進化する本能」などというものは、もともと存在しない。「成長」「進化」「発展」というようなことは、生物に外部から「力」――現状維持ないし「タヒぬ」本能を妨害しようとする妨害力――が加えられた結果生ずる現象にすぎない、と言うのです。
その「妨害力」のおおもとは、太陽エネルギーと地球内部の核エネルギー、自転・公転の運動エネルギーであり、それらに基いて起こる大気の風力、海水の波浪の力、気・水の熱エネルギーなどが、タヒんで無生物に戻ろうとする生命体の努力をさまたげ、生き続けさせてしまうのです。
Maximillian cabinet/Shutterstock/ 筑波大学
こうして、生命の誕生が繰り返される原始の熱水の海で、生まれた生命がただちに無生物質に戻ろうとする力と、それを妨げようとする外部の力(熱エネルギーなど)が釣り合うと、そのバランスのなかで、生命体は一定の期間存続するようになります。
このバランス状態は、外部からの力が恒常的に同じように加えられていることによって成り立っています。
ところが、ここで、たとえば太陽から放射されるエネルギーが減少して温度が下がるとか、逆に上がるとかして、バランスが崩れると、生命体は、もとの状態に戻る本能によって環境の変化を相殺しようとして体制を変えます。ここに、「進化」の起るきっかけが生ずるのです。
『あらゆる本能は、以前の状態を回復しようとする、という仮定を、徹底的に追究してみたいと思う。〔…〕
あらゆる有機的な本能は保守的で、〔…〕退行、つまり以前の状態の復活に向けられているものとすれば、われわれは有機体の発展の成果を、外部から妨害し、偏向させる影響のせいにしなければならない。原始的生物は、そもそもの発端から、変化することを欲しなかったであろうし、常に変わることのない事情〔環境――ギトン註〕のもとで、たえず同一の生活経路しか反復しなかったことであろう。
究極のところ、有機体の発展〔進化――ギトン註〕に刻印をきざみつけたものは、われわれの地球と、その太陽にたいする関係の発展史にほかなるまい。保守的な有機的本能は、この押しつけられた生活経路の変化〔環境の変化――ギトン註〕をことごとく受け入れ、反復のために保存しているのである。そのため、実はただ、古い目標を新旧のふたつながらの方法で追っているのに、何か変化と進歩を求める諸力があるかのような誤った印象を作り出しているのにちがいない。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.177-178.
「新旧のふたつながらの方法」とは、環境の変化が起きる前の現状維持の方法と、環境が変化した後で、環境の変化にもかかわらず前と同様の生存を続けるための・新しい現状維持の生存のしかたです。つまり、生命体が追求しているのは、常に・あくまでも現状維持であり、旧い生活状態を続けよう、「反復」しようとすることなのです。にもかかわらず、この時間の経過を外部から見ると、あたかも生命体が進化しようとしているかのように見えるのです。
『生命の目標〔…〕それは、生物がかつて棄て去った状態であり、しかも発展のあらゆる迂路をへてそれに復帰しようと努める古い出発点の状態であるに相違ない。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,p.178.
生物にとって、最も古い「出発点」とは、無機物・無生物の状態です。これに、あらゆる生物はいつかはタヒぬ、例外はない、という私たちが観察する経験的事実を加えるならば、「生命の究極的目標とは、タヒんで無機物に還ることである。」と言わざるをえないのです。
『過去のいつの時代かに、今日まだ想像することもできぬ〔ギトン註――外部からの〕力作用によって、生命のない物質の中に生物の特性がよびさまされた。〔…〕それ以前生命の無かった素材の中に当時発生した緊張は、平衡を取り戻そうと努力した。それは、無生物に還ろうとする最初の本能であった。そのころ生きていた物質にとって、タヒぬことはまだ容易であり、おそらく、若い生命の化学的構造で方向づけられた〔ギトン註――その〕短い生涯を終ったであろう。
長い時代にわたって、生ある物質は再三再四新たに創造されては簡単にタヒんでいったことであろう。こうしてついに、決定力をもつ外部の影響が変化して、生きながらえる物質を、原始的な生活経路からしだいに大きく偏向させ、タヒという目標に到達するまでにますます複雑な迂路をたどるように強いたのである。このタヒにいたる迂路は、保守的な本能によって忠実にまもられて、今日われわれに生命現象の姿を示しているのであろう。もし本能のもっぱら保守的な性質にもとづいて考えるならば、生命の由来と目標について、以上とは別の推測に到達することはできない。
〔…〕自己保存本能、権力への衝動、自己顕示の衝動など〔…〕それらは部分的衝動であって、有機体自身のタヒへの経路〔その種特有の経路――ギトン註〕を確実にし、無機体への復帰の他の可能性を内在的なものにとどめておく任務をもっているのであるが、全世界にさからっても自己を主張する有機体の不可解な努力は、』無機体へ還ろうとする本能とは、見たところ正反対で、それに関連づけるのは困難と思われなくもない。しかし、次のように構想してみることはできるだろう:『有機体は、それぞれの流儀にしたがってタヒぬことを望み、これら生命を守る番兵も、もとをただせばタヒに仕える衛兵であったのだ。このようにして、生命ある有機体は、生命の目標〔タヒ――ギトン註〕に、最も短い道筋』で(つまり短絡によって)到達させようとする『作用(危険)に、きわめてはげしく抵抗するというパラドックスが起こる。しかし、このような態度こそ、知的な努力とは』異なる『純粋に本能的な努力の特色を示しているのである。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.178-179.
つまり、生物にとって、「生命の危険」とは、「短絡(ショートカット)」であるがゆえに有害なのであり、生物はそれを避けようとして抵抗する。しかし、タヒぬこと――無機体に還ること――じたいは、生命の究極の目標そのものだとフロイトは言うのです。「生」とは、タヒに至る迂路であって、高等生物ほどその迂路は複雑で長く、生命自身は、自らの種にプログラムされた特有の迂路を忠実に守って――それじたいが、保守的本能の帰結――目標(タヒ)に至ろうとする。
【29】 ジーグムント・フロイト
――「タヒの欲動」と「性的本能」
前節のようにして、フロイトは、自己保存本能や自己顕示欲のようなものまで、「タヒの衝動」の変形として説明できるとするのです。
しかしながら、高等生物(多細胞生物)については、「タヒの衝動」と並んで別の基本的本能も具えられているとします。それは、「性的本能」ないし「性的欲動」です。というのは、多細胞生物の身体は、「胚細胞(生殖細胞)」と、その他の生活細胞――という2つの部分からなっているからです。
『すべての有機体が、たゆみない発展にかりたてる外的な強制に屈服したわけではない。多くの有機体が、低い段階で自己を現在まで守り通すことに成功しているのである。〔…〕高等な生物の複雑な身体の構成要素となっている有機体〔…〕それらのうちの若干、たとえば胚細胞は、おそらく生命ある物質の始源の構造を保持していて、遺伝によって受けついだり、あらたに獲得したりした、あらゆる本能の素質を負わされながら、一定期間の後には全有機体から離脱する。それらに独自の存在を可能にするものは、おそらくこれら2つの特性〔なお保持している始源の構造と、新たに獲得された素質――ギトン註〕にほかならぬであろう。適当な条件の下におかれると、それらはみずから発展しはじめる。つまり、自己の発生を負うている演劇〔個体の発生・成長・生殖――ギトン註〕を繰り返すのである。そしてこの演劇は、その物体のある部分がふたたび終局まで発展してゆき、一方、他の部分は新しい胚種としてあらためて発展の発端に立ち戻るまでつづく。このようにして、胚細胞は〔…〕われわれには潜在的な不滅の力とみえるに相違ない性質〔個体の生命を子孫に延長すること――ギトン註〕を、生物のために獲得している。胚細胞が、他の・類似してはいるが別個のものである細胞との融合によって、この活動のための力を与えられる事実〔…〕は、われわれにとってきわめて意味深い。
個体以上に長い生命を保つこれらの要素的有機体〔精子,卵子など――ギトン註〕の運命を配慮し、それが外界の刺激〔強すぎれば破壊に至る――ギトン註〕に対して無防備であるために、その安全な保護のために計り、他の胚細胞との遭遇を促すなどの任務をもった本能が集まって、一群の性本能を形成している。これらの本能は生物の以前の状態を回復する点では、他の衝動とおなじ意味で保守的であるが、外的な影響にたいしてとくに強い抵抗を示す点ではいっそう保守的であり、また生命そのものをさらに長期にわたって保存するのであるから、より広い意味でも保守的である。つまり性的本能は本来、生の本能である。つまり性的本能は、タヒにみちびく他の本能の意図を阻むのであって、性的本能とその他の本能のあいだには、〔ギトン註――フロイトらの〕神経症学説がつとに重要なものとみとめた対立関係〔快感原則vs現実原則、など――ギトン註〕があることを物語っている。それは、さながら有機体の生命における動的なリズムのようなものである。一方の本能群〔「タヒの衝動」など――ギトン註〕は、生の究極目標にできるだけはやく到達するために、前方へ突き進み、他の本能群〔「性的本能」など――ギトン註〕は、この経路のある地点で跳ね返って、この道程を一定地点からもう一度繰り返し、こうしてこの経路の持続を延長しようとする。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.179-180.
こうしてフロイトは、「自我本能=タヒの本能と、性的本能=生の本能」の区別、「生の本能とタヒの本能の大きな対立」を考察の基礎に据えます。
『「自我本能」と性的本能、前者はタヒを、後者は生の継続を強いるものである』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,p.181.
そうすると、「快感原則」は、「性的本能=生の本能」のほうに親近性があるように思われます。しかし、「性的本能」が現れるのは、さきの発生的考察からすれば、胚細胞の発生をきっかけとするもので、胚細胞による生殖をまだ知らない単細胞生物の場合には、「快感原則」が生体の衝動を支配することもない、とも考えられます。「快感原則」以前の生命体は、もっぱら「タヒの本能」にのみ支配されているのでしょうか?
だとすると、とてもパラドキシカルな理論になってゆくように思われます。が、フロイトは、この論文の終りでは、「快感原則」をも「タヒの本能」からみちびく方向に、解決を求めているように思われます:
『以前の状態を回復しようとするのが、現実に本能の一般的な性質であるとすれば、精神生活において多くの事象が快感原則の支配を受けずに成就されることは、あやしむにたりないであろう。〔…〕
快感原則は一つの傾向であって、ある機能に役立つことになる。その機能とは、心的装置に興奮が起こらぬようにするか、あるいはその興奮の量を一定に、またはできるだけ低めに保つことである〔過度の興奮や急激な興奮の上昇は、生体を危機にさらす。つまり「不快」だから。――ギトン註〕。〔…〕こんなふうに限定された機能は、無機的世界の静止状態にもどるという、全生物のもっとも普遍的な努力の一翼を担っているものとみとめることができる。われわれの達しうる最大の快感、つまり性的行為の快感は、高度にたかまった興奮の瞬間的な消滅と結びついていることを、誰もが知っている。しかし、衝動興奮の拘束は準備的な機能であって、興奮を放出の快感において最終的に解消するように調節するものであろう。
〔…〕快感原則は、まさにタヒの本能に奉仕するもののように思われる。それが、両種の本能によって危険とみとめられる外部からの刺激を警戒することは言うまでもないが、また、とくに生の課題を困難にすることをめざす内部からの刺激の増大を警戒する。』
小此木啓吾・訳「快感原則の彼岸」, in:『フロイト著作集』,pp.193-194.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!