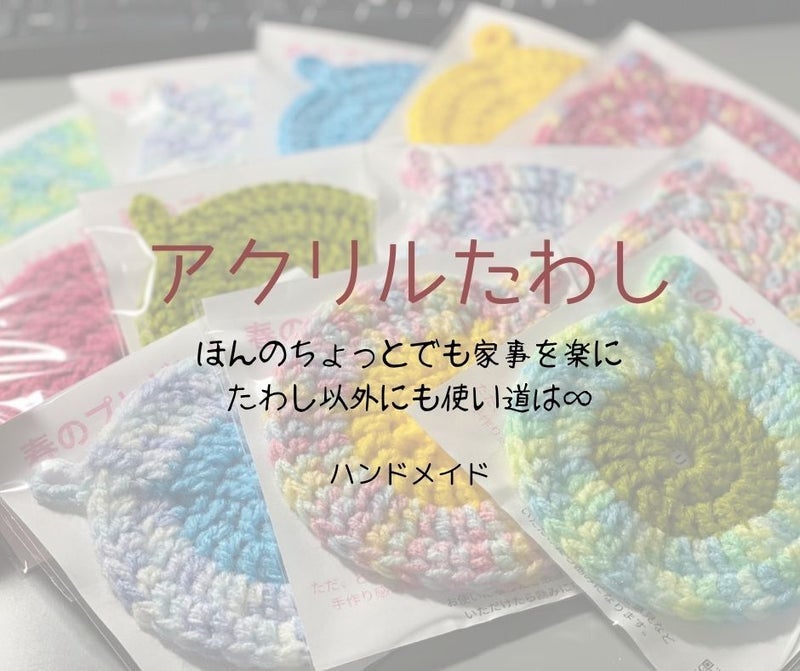(株)大共建設・きねつ工房のつくりんです。
3/20(木)から二十四節気・春分にはいっていますね
3/20(木)春分の日は宇宙元旦ともいわれ、この日から新しい一年が始まるから何かを始めようと思って準備をしている人も多っかたのでは?
春分の期間は、確定申告や年度末などもあり、卒業、卒園などで忙しい時期。
そうこうしているうちにあっという間に新年度、新しい環境での生活のスタートも始まり、落ち着かない時期でもありますよね~。
その期間の家しごとといえば
一年間の区切りとなる年度末は、たまった書類を整理するのに最適。
期日の過ぎたお知らせ、完了して保管する必要のない書類などはこの期間に手放しておくと新年度のスタートがスムーズになっていきますよ。
それでも、時間が……と思うなら
保管する書類などを入れておく保存ボックスを作って、一時置き場を作っておくのもおすすめです。
冬用寝具や暖房器具もそろそろしまってもいいころ。
とはいえ、これからやってくる梅雨の時期は、肌寒さを感じることもあるので、その時期に使えるものはすぐに取りだせるようにしまっておくといいですよ。
わたしは、布団を冬は2枚掛け、春夏は1枚掛けとして一年間同じかけ布団を使っています。
いまは、羽毛布団など軽いものもあるので一年間通して使うことも、掛ける枚数で調整することもしやすくなっているので、しまう、出すことが面倒に感じる人は見なおしてみるのもいいかもしれません。
さて、ここからは少し春分のお話をしていきます。
春分の日は太陽は赤道上にあり、地球のどこにいても昼と夜の長さが同じになる日ですが、厳密にいうと実際には昼のほうが少し長いといわれています。
この日が国民の祝日になったのは、戦後の1948年に公布、施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で制定され、祝日法上の春分日は、毎年3月20日~21日ごろのいずれか1日で、実際には日付はきまっていません。
祝日法の春分の日での定義は、太陽が春分点を通過する瞬間が「春分」で、春分を含む日のことを「春分日」といわれ「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。
この日は、道端の花などをゆっくりと愛でる時間をとったり、庭の植物、ベランダの花たちのお手入れをするのもいいですね。
春分の日のもとは旧法にあった「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」から改称されました。
春季皇霊祭とは、現在でも行われている宮中祭祀の一つで、毎年2回、春分の日と秋分の日(秋季皇霊祭)に斎行される大祭です。
大祭とは、皇居の宮中三殿で天皇陛下自らが斎行し、御告文(おつげぶみ)を奏上する祭祀のことで、この日は歴代の天皇、皇族の御霊が祀られる皇霊殿にて「春季皇霊祭の儀」など祭祀行事が行われています。
この祭祀は、戦前の日本では非常に重要な儀式の一つとされたことから国民の祝日になったといわれています。
春分の日は、お彼岸の中日でもあります
中日を中心にお彼岸期間中は、ご先祖様への感謝の意味を込め、お墓参りや仏壇の掃除、お供えなどの供養を行うだけでなく、じぶん自身の日頃の行いを振り返り、見つめ直すのが古くからの習わしといわれています。
わたしは、数年前からずっと行きたいと思っていた父の田舎・鹿児島にお墓参りに伺ってきました。
改めて、父が育った家で過ごした時間はなんとも言いようのない素敵な時間でした。
なんとなく、幼いころの父を想像したり、どんなふうに暮らしていたのかななんて空想してみたりと、じぶんのご先祖様、父と少し重なった気持ちになりました。
この期間は、じぶん自身を見つめなおし、これからの一年の軌道修正をしたり、新しく始めること、手放していくことなどを決めてみるのもいい時期ですね。
そして、春分の日は、太陽が真東から出て真西に沈む日
浄土思想では、極楽浄土は西方にあり西方に沈む太陽を礼拝することが習わしとされ、煩悩を払うため西に沈む太陽に祈りを捧げ、極楽浄土へ思いをはせる日でもあります。
春分の日、秋分の日は「此岸と彼岸が最も通じやすい日」と考えられ、この日に西に向かって拝むと、功徳が施されるとも信じられたことから、春分の中日を中心に供養を行うようになったといわれています。
春分とは季節の指標として使われる二十四節気の一つで、春の中間に当たり、農業が中心の古代の生活において、農作物の作付け、収穫を行う際の時期を見極める、1年間の農作業のスケジュールにより正確を期すために、細かく季節を分ける必要がありました。
春分を目安に、農作業を本格的に始めることが多いともいわれています。
日常でも、寒さに耐えていた草木が徐々に芽吹くのを見ると、春の到来を感じることもあり、春分の日が自然をたたえ、生物をいつくしむ日とされているのだとか
そして、春分の日には、太陽が北緯35度22分のラインを真東から昇って真西に沈むとき、西から出雲大社(島根県)、大山(鳥取県)、元伊勢(京都府)、竹生島(滋賀県)、七面山(山梨県)、富士山、寒川神社(神奈川県)、玉前神社(千葉県)の上を太陽が通り、一直線で結ばれる現象は“ご来光の道”と呼ばれています
春分には、ぼたもち、つくし、はっさく、はまぐり、ほたて、ふき、フキノトウなどの旬の食材をいただくのもいいですね
つくしは意外と身近にひょっこりと顔をだしていることもあるので、バター醤油などでいただくとおいしいですよ
お部屋などに飾るなら、この時期はミモザ、ラナンキュラス、コデマリ、チューリップなどもいいですね
春分期間は4/3(木)まで
新しいことを始める準備も良し、これまでのことを振り返り手放していくのもよし、この期間を今年一年のスタートと考えてみるのもいいですね。
わたしも、この期間になんとな~く、ぼんやりと浮かんでいることを書き出し、はっきりしたビジョンにしていきたいなと思っています。
お知らせ