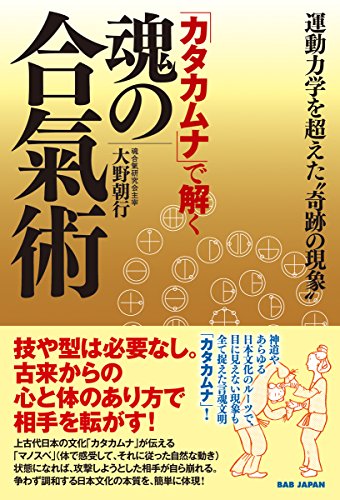大野先生よりカタカムナの勉強が続いております。
カタカムナって何が書いてあるのかと言えば、「(現代ではまだ行き着いていない)物理法則」、とかいう理解でいましたが、まあそうなのだと思いますが、現在のわたしの言葉にすると、「わたしたち人間とは何なのか?」ということが、言葉を変え、説明を変え、書いてあるように思えます。(勉強している量は非常に少ないので、先生のチョイスがそう思わせるのかもしれませんが。)
なにせ、これが文字であり、ウタであります。
そして表の世界と裏の世界(モノとして現れているもの、いないもの)、モノとして現れていないものがモノとして現れるまでのことを説明していたりします。
でも不思議とこの理論は、私たちに自然と備わっている、(人格神ではない)あらゆるものの中に神をみる、「八百万の神」の神を表現していると思います。
これが日本人の原点であることは、間違い無いと思うのです。
これを解読なさった方は楢崎皐月さんという科学者で、原子爆弾を無力化させる研究をしていたとか。そしてそのお弟子さんの宇野多美恵さんという方が「相似象学会誌」を通して、学んだことをまとめられたようです。
ウタどころか、この学会誌でさえ、読んでいくのが大変です。
というのは、私たちの理解は現代の西洋科学、西洋論理がベースになっているので、それでは理解できないからです。
ベースから組み立て直さなくてはなりません。
ベースどころか素材の考え方からして違うのです。
多美恵さんは、これは頭で理解できるものではない、感受性を鍛えて、直感で分かるようにすることだ、とおっしゃっております。
そして、「感受性とは何か」ということについて、8冊も本を書いている(先生曰く)そうなのです。
そして先日、その中の一部を学んだときに、「ああわたしって感受性というものについて何も考えたことがなかったのに使ってた。」ということに氣付きました。
感性とか感受性とか、どこから来るのかわからないけど、大まかなイメージで使っていたんですね。(使っている言葉の大半はこんなものかもしれませんが。)
このようなことを宇野さんは「観念の能力」と呼んでいて、それが人間には備わっているが、「この自分の脳の能力の限界(くせ)」を知っていないと、概要を読んだだけでわかった気になり、本当は、自分はまだ、何もわかっていないことに、気がつかず、読み流してしまう危険がある、と文章のはじめに書いてあります。
ソクラテスの「無知の知」みたいですね。
「脳のくせ」とは、びっくりです。
でも、かなり鋭いところだと思います。
だいたい「伝える」ことの難しさは、こういうところにあるからかもしれません。
あるいは理解の難しさ、とても言いましょうか。
カラダ(動き方)の癖さえ、アレクサンダー・テクニークを知らなければ、一生そのままになっていたものを、
脳の癖とは…。
これを知り、変えてゆくのが人としての成長、進化なのかもしれません。
でも考えてみたら、アレクサンダー・テクニークの真の目的もこういうことだと思っているのですが。