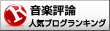このアルバムはアメリカの国営放送局の Voice of America の国際放送サービス部門が残していたオープン・リール・テープの音源をデジタル変換作業していた際に発見されたものです。Monk が Bud Powell のヘロンイン所持を庇ってキャバレーカードを没収されたのが1951年、その後NYエリアでの演奏活動が出来ずにいたが、マネージャーの Harry Colomby と ニカ夫人の尽力で1957年に奪回し、NYでの活動を再開し、Coltrane と1957年7月18日から12月26日までマンハッタンの Five Spot で活動することになります。それが恐ろしく音の悪い未発表音源の The Thelonious Monk Quartet Featuring John Coltrane / Live at the Five Spot Discovery! (1957) で、そのほか、同年の4月6月7月で、二人のセッションが録音されているのが、Thelonious Monk With John Coltrane (1957-1958)、Thelonious Monk Septet / Monk's Music (1957) になります(私の所持音源では)
Coltrane も有名なヘロインのジャンキーで、1957年にマイルス・バンドを1回クビになっています。1957年のはじめ、Café Bohemia 出演の時、Coltrane が全く無反応だったのにマイルスは頭をひっぱたき、腹にパンチをいれ仲裁に入ったのが Monk だったとも。自身は薬物はやっていなくても、色々な事件の影に薬物があり、この時代のアメリカは映画のような世界だったようです。ニカ男爵夫人の著書で、Monk の3つの願いは、1.音楽的に成功すること、2.幸せな家庭をもつこと 3.君のようなクレイジーな友人をもつこと。ニカ夫人以外の友達もクレイジーだったようですが。
さて、この録音に戻ります。1957年11月にNYの Carnegie Hall で行われたライブ録音です。レギュラー出演の Five Spot とは別の場所でのライブ録音となっています。【Early Show】は、PM 8:30 ですから、遅い開始となります。このアルバムに収録は、Monk's Mood、Evidence、Crepuscule With Nellie、Nutty、Epistrophy の5曲で、1時間に満たないので、おそらく録音全てが公開されてはいないと思うので、ほとぼり冷めた頃に完全版が発売されるのでしょう。多分未だ出ていないと思います。音は結構良いのですが不満は若干あり、最後に書いときます。Monk's Mood は、最初は長めのピアノソロから始まり、 Coltrane が吹きまくる、ほぼデュオで始まります。ベースが弓弾きで控えめに入っていますがドラムは休みで幻想的な曲になっていて、まさにショーが始まる演出もばっちりです。Evidence では、ドラムも入ったキッチリとしたコンボ演奏です。Coltrane が相変わらず吹きまくるので、Monk の独特の和音と入れるタイミングは誇張しすぎず、調和のとれたバッキング。でもピアノソロ部分では思いっきり、あのタイミングを入れてくるので、それに合わせ Coltrane が単音を入れてきますが、Monk に少し遅れて入れてくる掛け合いが何とも楽しいです。Crepuscule With Nellie では、個人技よりもバンド・アンサンブルとしてモンク節の効いた演奏になっています。盛り上がってきたところで、Nutty です。ドラムの
Shadow Wilson が、ドシャっとした音ですが上手い方だと、ここで気づきます。いつもの
Roy Haynes だと、もう少し四角い感じでリズムキープに徹する感じと対照的で、次のEpistrophy だと、もっと顕著に違います。シンバル・ワークとか曲の随所で細かい芸があります。でも演奏的には上手すぎて、どこか、ぎこちない感じがするような、いつもの演奏も良いもんなんだなと、聴きながら思ってしまいました。
CDだと盤は変わりませんが【Late Show】は午前0時スタートです。電車で帰るという感覚が無いのでしょう、NYの遊び方は時間の感覚が日本と異なるようで遅すぎです。Bye-Ya 正統派なバップで、ここでもドラムのパーカッションが居るかのような細かな技、Coltrane の流れ出る音符に、Monk の感性が一つの音楽を創り出し説得力があります。と思っていたら次の Sweet And Lovely の朗々とした演奏もまた別の趣。長めの緩やかな演奏を静かに聴いていたら、途中からテンポ・アップにハッとさせられるのも面白い仕掛けかなと思います。ここら辺は Coltrane が居るならではの構成ではないでしょうか。長めの9分34秒です。そしてBlue Monk は、お馴染みのモンク・ナンバー。演奏し慣れている感じが十分に伝わる軽々した演奏で、テーマとソロ部分も変わったことはせずに、きっちりと演奏しきっていて安定感があります。最後は Early Show のラストでもあった、Epistrophy で締めくくりです。同じ曲でありますが Early Show はパーカッシブなイントロであったのに対し、Late Show では、アーシーなアレンジです。このタイプの演奏は Monk では珍しい気がします。ピアノソロに入ったところの2分24秒でフェイド・アウトはもったいない。あと30秒ぐらいは欲しかったです。🎶
聴き終わりましたが、残念なことは、本CDは、PCでは普通に再生できない東芝EMIのセキュアCDであったこと。PCでの再生用のプログラムも動かず、私のPCでは再生できませんでしたが、幸いこのアルバムは別の方法で音源が入手できました。しかしこのほかに、Ben Harper / Both Of The Gun, Sony Music からの 小沼ようすけ / Jazz'n' Pop なんかは、全く歯が立ちませんので、盤はあるのに1回も聴けない状態です。よく見て買えよって話しですが、この盤を購入した人だけ「音質は落ちるけどストリーミングできるIDを入れておく」とかの何か救済措置はできないもんなのか。著作権は守らなければならないのでコピープロテクトは良いとしても、機器によっては全く再生できず、データを見ることもできないでリスナーを狭めるような技術の片手落ちのような音源の作り方はどうなのかな、日本盤を買わなければ良かったな、と思ってしまいます。残念
piano : Thelonious Monk
tenor sax : John Coltrane
bass : Ahmed Abdul-Malik
drums : Shadow Wilson
producer (concert) : Kenneth Lee Karpe
recorded by, engineer (Voice Of America) : Harry Hochberg
art direction, design : Burton Yount
ilustration (cover) : Felix Sockwell
recorded on November 29, 1957 by Voice of America at Carnegie Hall, New York City.
This concert was produced for the benefit of the Morningside Community Center.
The original recordings were engineered by Voice of America.
Tape preserved and provided from the collections of the Library of Congress.
24-bit/192 kHz digital transfer from the original 15 ips mono analog tape,
Sonic Restoration, Forensic Editing™, and Pre-Mastering by Transfer Master.
【Early Show PM8:30】
1. Monk's Mood / Thelonious Monk
2. Evidence / Thelonious Monk
3. Crepuscule With Nellie / Thelonious Monk
4. Nutty / Thelonious Monk
5. Epistrophy / Kenny Clarke, Thelonious Monk
【Late Show AM0:00】
6. Bye-Ya / Thelonious Monk
7. Sweet And Lovely / Charles N. Daniels, Gus Arnheim, Harry Tobias
8. Blue Monk / Thelonious Monk
9. Epistrophy (Incomplete) / Kenny Clarke, Thelonious Monk
▶ Evidence
▶ Nutty