
当ブログへお越しくださるみなさま。
ご無沙汰しております。
なかなか更新できずにいる中、ご来訪ありがとうございます^^
さて、京都近代美術館で開催された東山魁夷展に行ってきました(このあと東京に巡回)。生誕110年を記念した展覧会は、習作やスケッチも含めると主な画業がほぼ網羅されており、とても見ごたえがありました。
横浜美術館で初めて画伯の作品に出会ってから14年。その後、東京での展覧会や他の美術館、千葉の記念館、そして最近では唐招提寺と、折に触れて作品を鑑賞してきましたが、『残照』や『花明り』など大好きな作品の多くはほとんど観る機会に恵まれず、今回再会できたのは嬉しいかぎりです。
同時に、『白夜光』や『白馬の森』など、以前は心に残らなかったのに、今回初めて魅かれる絵もありました。私自身が歳を重ねることで、その作品を描いた頃の画伯の年齢に近づき、これまではみえなかった画伯の思いや意図が理解できるようになってきたのかもしれません。
『白夜光』は、北欧特有の寒々とした空気がなじめなかったのですが、今回は写実的とも言える暗く縹渺たる森林の、遠い水面に宿る、細く、けれども鋼のように研ぎ澄まされた光がとても美しかった。挑戦し続ける画伯の強い意志を感じました。
『白馬の森』は目にした瞬間、その清らかなたたずまいに心を奪われました。白い馬は親交の深かった川端康成氏の死後に現れるようになったと聞いたことがありますが、今回改めて思うのは、描かれているのはこちら側と彼我との合間の世界であり、同時に心象風景でもあるということです。50歳代、60歳代の作品は、野心も含めて現世の活力が漲っていて、旅で訪れた土地のナマっぽい手触りを感じるのですが、70歳代に入ると、そうしたものがそぎ落とされて、ベクトルが外側から内側に向かいます。白馬はその景色の中にいて、いつも手の届かないところに立っている。そのすがたは早世した家族や川端氏の魂の化身のようにも見えます。自分と深いつながりを持つ人たちの多くがあちら側に居るなんて悲しいことですね。いつかは自分も訪れる世界。老いていく身を自覚しながら生き続けていくことの苦しさ。そこから生まれる祈り。白馬はある日突然出てきて、1年くらいでふっといなくなったそうです。祈りの中からそれでも生きるべき道が見えたとき、白馬はその役目を終えた気がします。
おなじみの作品たち以外に楽しみにしていたのは、後に『京洛四季』にまとめられた一連の京都のスケッチです。さすが京都開催! 展示替えを含めると、相当な数が展示されていました。(ちなみに本展覧会の図録には地図が掲載され、すべてのスケッチの描かれた場所がわかるようになっています。)当ブログで『東山魁夷をめぐる旅』を書くにあたり何度も見返した作品たちですが、原画を観るのは初めてです。二条城の石垣や化野念仏寺の地蔵など、造形に興味があるものは鉛筆で丹念にスケッチ、散り紅葉など色の美しいものは絵筆でさらりと色をのせてある。宵山の幽玄や町家に軒先の古道具など、画伯が心ひかれた景色がクロースアップで率直に描かれ、観ていて飽きません。
スケッチに続いて並んでいるのは、匂うようにあでやかな春の山桜に、あおが瑞々しい竹林、鮮やかな秋の紅葉の手前で朽ちる葉、そして年の瀬に静かに降る雪(画伯の描く雪のリズムが大好きです)など、京都の四季を描いた作品が続きます。ずらりと並んだ作品たちを眺めていると、画材を抱えて、てくてくと歩き続ける画伯の姿が浮かび上がってきます。京の四季の美しさを愛で、いにしえの職人たちの技に感嘆し、この町で営まれる人々の暮らしを慈しむ。画伯の旅の軌跡を辿るとき、鑑賞者自身の中にも自然と京都への愛着が湧きあがって、このような景色がこの先ずっと千年も続いて欲しいと心から願うようになります。
この展覧会の目玉の一つは唐招提寺の障壁画ですが、以前こちらのブログで詳しくご紹介したので今回は省きます。ひとつ言えるのはやはり別格でした! 芸術は時空を超えた交流を可能にする。画伯の鑑真和上への心遣いが沁みる作品です。
14年前には存在を信じて疑わなかった画伯の描く『日本の原風景』ですが、今回、緑豊かな山河や京都の風景を見て感じたのは大きな危機感でした。私が京都に行き始めて4年弱ぐらいですが、そのわずかの間にも京都の町はどんどん変わっています。そもそも『年暮る』に描かれた民家の風景は、画伯が執筆当時にすでに過去の景色だったそうです。近年の温暖化を考えると、豊かな緑も、降りしきる雪も、いつか見られなくなる日が来るかもしれません。
次に画伯の作品に出会えるのがいつかはわかりませんが、その時にも「美しい日本の風景」と思える未来を切に願います。










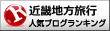

 と心底感心したことがあります。
と心底感心したことがあります。 仲良いんだなあ、と思いながら笑っていました。
仲良いんだなあ、と思いながら笑っていました。


 未だ布に包まれているもののお姿を間近で見る絶好のチャンス。とは言え立ち上がる姿は「引き」でみたい! 悩んだ末、今年は(笑)その場でじっと我慢を選択です。
未だ布に包まれているもののお姿を間近で見る絶好のチャンス。とは言え立ち上がる姿は「引き」でみたい! 悩んだ末、今年は(笑)その場でじっと我慢を選択です。



















 見たい桜は数あれど、なかなかその盛りには巡り合えません。まこと花の命は短くて、出会いは貴重なのです。満開ではなくても、今日咲いている桜に出会えたことはささやかな幸せと噛みしめるべきですね。
見たい桜は数あれど、なかなかその盛りには巡り合えません。まこと花の命は短くて、出会いは貴重なのです。満開ではなくても、今日咲いている桜に出会えたことはささやかな幸せと噛みしめるべきですね。












