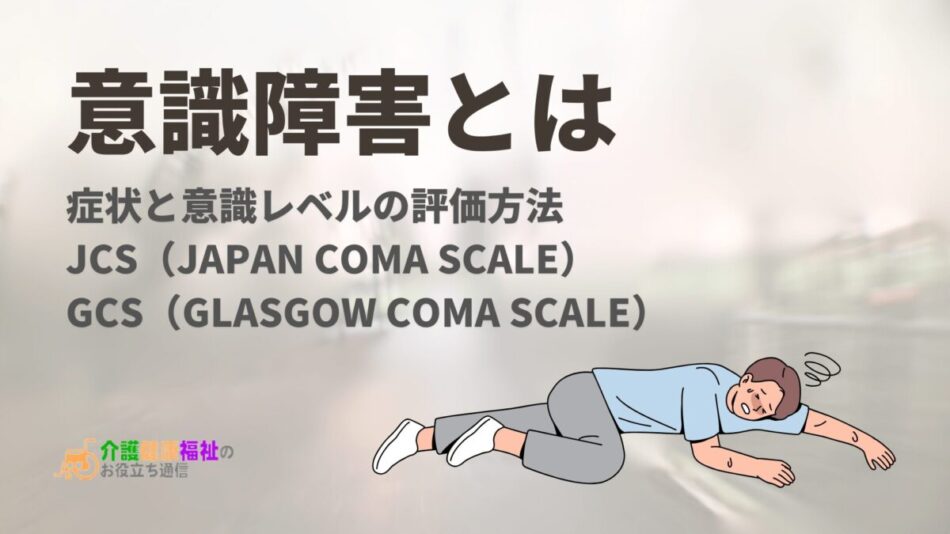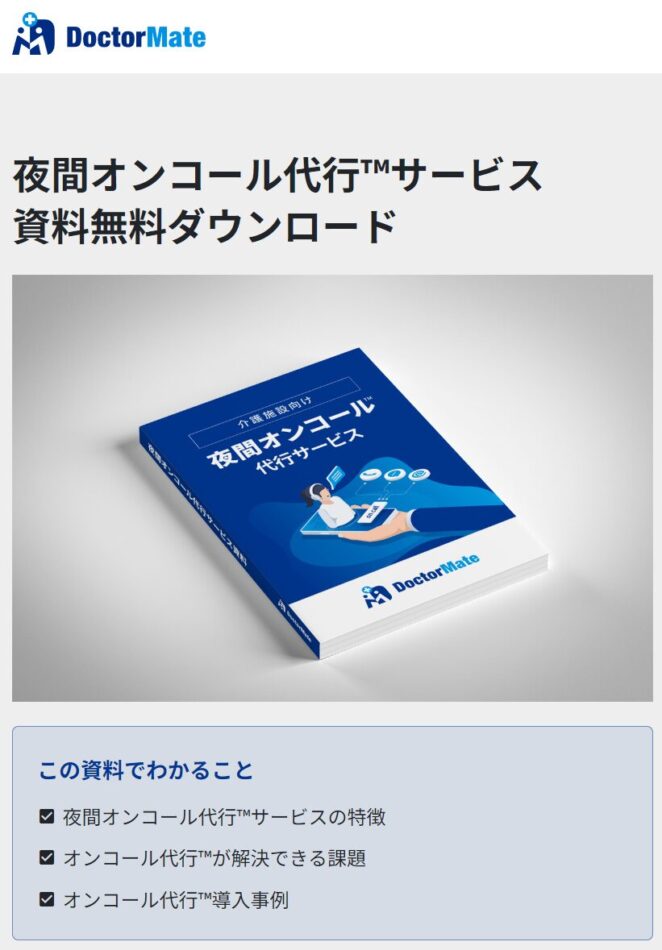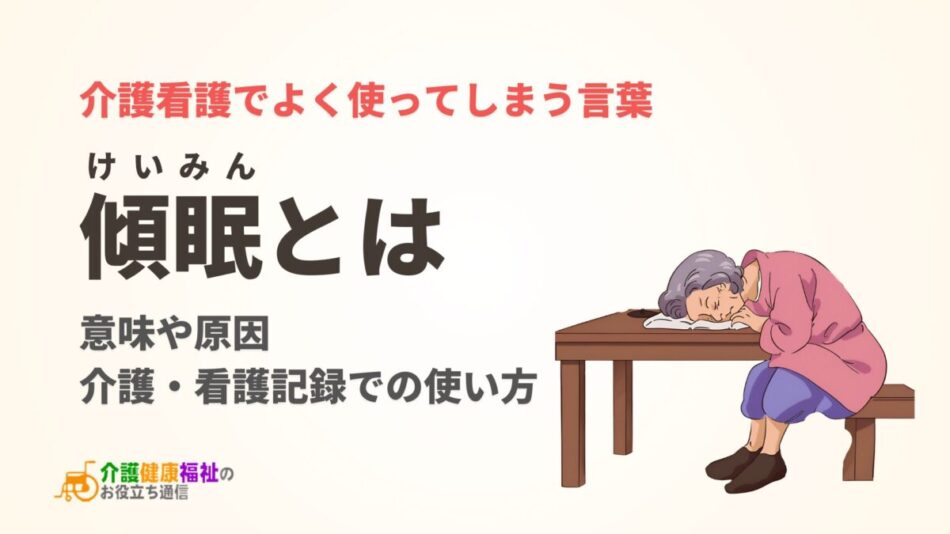
「傾眠」とは、患者が意識が低下し、眠りに傾きやすい状態を指します。傾眠傾向の状態はさまざまな原因によって引き起こされ、適切な介護や看護が必要です。本記事では、傾眠の意味や原因、介護・看護記録での適切な取り扱いについて解説します。
このページの目次
傾眠傾向とは
高齢者によく見られる軽度の意識障害で、外部から軽い刺激で意識を取り戻す状態を指します。傾眠は意識障害の最軽度であり、様々な原因により引き起こされます。傾眠状態では、被介護者は眠っているように見えるが、外部からの刺激によって一時的に目を覚まし、応答したり意識を取り戻したりすることを意味することが多いです。
しかし、「傾眠」という言葉は、介護や看護の現場にいると多用されていますが、医学的に定義されている言葉ではなく、眠気でウトウトしている状態を端的に表すための業界用語のようなものなので、この点は注意が必要です。
意識レベル(意識障害)の一般的な評価方法
意識障害の分類には、意識の混濁の度合いによって、傾眠、昏迷・半昏睡・昏睡などの表現があります。ただし、傾眠・昏迷・半昏睡・昏睡という分け方は日本語でわかりやすく表現した場合の表現方法です。
一般的に意識状態の評価には、ジャパンコーマスケール(Japan Coma Scale:JCS)や、グラスゴーコーマスケール(Glasgow Coma Scale:GCS)を使用します。
Japan Coma Scale(JCS)は、①覚醒している ②刺激に応じて一時的に覚醒する ③刺激しても覚醒しない という点をみます。
Glasgow Coma Scale(GCS)は、①開眼機能(目が開くか) ②言語機能(会話が成立するか) ③運動機能(言われたことが分かって身体を動かせるか) という点をみます。
傾眠の症状
傾眠は、本当は起きているなくてはならない時間帯にウトウト眠りそうになっている、半分寝ているような感じの症状です。特に健康問題が無いようなお年寄りでも、さっきまで起きていたのに気づいたら寝ている、話しながらうとうと寝てしまう、といったこともあるので高齢者に特に見られる症状です。
一般的には深刻な問題ではありませんが、急に傾眠状態になった場合や、傾眠傾向が続く場合は注意が必要です。傾眠状態が続くと、ご利用者・患者は注意力が散漫になったり、意欲が低下したりすることがあり、事故につながります。疾患や薬剤が原因で傾眠が起きている場合には、より深刻な病気の前兆である可能性もあります。このような症状が見られた場合には、原因を特定し、適切な対処法を見つけることが重要です。
傾眠の原因
傾眠の原因は様々であり、主な要因の1つは認知症です。
認知症の患者は、無気力状態や睡眠リズムの乱れによって傾眠状態に陥りやすくなります。認知症の患者は日常生活において意識を集中することが難しく、傾眠の状態になりやすい傾向があります。
また、脱水症状や慢性硬膜下血腫、内科的疾患といった状態も傾眠を引き起こすことがあります。高齢者は水分摂取量が不足しがちであり、特に夏場や運動後などで脱水症状が起
さらに、薬の副作用も傾眠傾向の要因として挙げられます。高齢者は複数の薬を服用していることが一般的であり、これらの薬が相互作用を起こして傾眠を引き起こす可能性があります。特に高齢者は薬の代謝や排泄が低下しているため、薬の効果が強く現れることがあります。そのため、定期的な薬剤管理や医師とのコミュニケーションが重要です。
傾眠状態が続く場合には、介護や看護の現場で適切な対策が必要です。被介護者に対して話しかけることや、日中に体を動かすこと、こまめな水分補給をすることが重要です。また、薬の調整や食事の見直し、見守りや支援の提供、時間を決めて昼寝をするなどの対策が効果的です。
傾眠状態は医療機関での相談が必要な場合もあります。早めの対応や適切な治療を受けることが、ご利用者・患者の健康状態を改善する上で重要です。介護記録や看護記録では、「傾眠」という用語を使用し、症状や対処法を正確に記録することが大切です。
傾眠傾向の対策
傾眠傾向が見られた際には、体を動かす、水分補給、薬の調整、食事見直し、昼寝の管理などの対策が重要です。さらに、食事中の誤嚥や転倒リスクにも十分配慮する必要があります。
体を動かすことは、傾眠状態を改善するための重要な対策の一つです。高齢者や認知症患者は身体活動が少なくなりやすいため、定期的に体操や散歩などの適度な運動を行うことが必要です。これにより、血行が促進され、認知機能や注意力の向上が期待できます。正しい体を動かすことをの管理と合わせて、睡眠が取れているかや、体力的に日中のお昼寝が必要なのかについても観察が必要です。睡眠が取れていなければ誰でも日中にウトウトしてしてうたた寝してしまうことはあります。そのような中で無理やり体動かしてもらっても逆効果です。
水分補給も傾眠傾向の改善に不可欠です。高齢者は脱水症状になりやすく、これが傾眠の原因になることもあります。こまめな水分補給を心がけることで、脱水症状を予防し、傾眠状態を改善することができます。
薬の調整も重要な対策の一つです。傾眠傾向がある場合、薬の副作用が原因であることが考えられます。特に、高齢者の場合には意欲が低下したり精神状態が不安定だったりした場合に向精神薬や抗不安薬が処方されている場合が多くあります。医師と相談し、適切な薬の使用や投薬量の見直しを行うことで、傾眠状態を改善することが可能な場合もあります。
食事見直しも傾眠傾向の対策に欠かせません。栄養バランスの取れた食事を摂ることは、高齢者の健康状態を維持するために重要です。特に、タンパク質やビタミン、ミネラルを十分に摂取することで、認知機能や体力の向上が期待できます。
昼寝の管理も重要な対策の一つです。昼寝の時間や頻度によっては、夜間の睡眠リズムを乱す原因となります。睡眠障害が発生していたりして夜中になかなか寝付けずに夜型の生活になってしまっている場合もあります。適度な昼寝の時間を設けることで、日中の眠気を解消し、夜間の睡眠の質を高めることができます。日中の傾眠傾向が気になっているご利用者・患者さんの場合には、夜勤帯の職員さんと連携して夜寝れているか少し念入りに確認してもらうなども有効な場合があります。
食事中の誤嚥や転倒リスクについても、傾眠が原因で発生する事故を予防する対策として重要です。高齢者や認知症患者は、誤嚥や転倒による怪我のリスクが高まっています。食事中は適切な姿勢や顎の動きを確認し、食事をサポートすることで誤嚥を予防することが重要です。また、部屋の環境を整え、転倒予防策を講じることで、安全性を確保することが必要です。
傾眠状態について医師への相談
傾眠傾向が見られた場合は、早めに医療機関や主治医へ相談し適切な対応を行うことが重要です。正しい理解と適切なケアが必要です。
医師への相談を行う際には、まずは症状やその状況を詳細に説明することが重要です。医師は検査や評価を通じて、傾眠の原因を特定し、適切な治療やケアが提供されることが期待されますが、介護施設や病院の場合には、ここまで述べてきたような「夜は眠れているか」「どんな薬を飲んでいるか」「傾眠傾向とは具体的にどんな状態になっているのか」「傾眠になっていて何が困っているのか」「昼寝もしているか」「水分は取れているか」などの情報を求められます。医師としても、必要な情報が集まると傾眠の原因を対処方法を導きやすくなるため、介護看護食としては、
介護記録・看護記録での「傾眠」の使い方
介護記録や看護記録では、「傾眠」という用語を使いがちです。しかし、記録に書かれている「傾眠傾向」や症状や対処法を正確かつ適切に記録する必要があります。ここまで傾眠について色々紹介してきましたが、冒頭に述べたように傾眠という言葉は医学的に定義された言葉ではありません。
スタッフ同士での情報共有としての傾眠という言葉を使う時の配慮
介護記録や看護記録で記録するときには、ただ「傾眠傾向」とだけ書かれていることが続くのはあまりよくないです。書き方はいろいろありますが、人間何にもやることが無くてただその場所にいてと言われたら寝ちゃおうと思いますし、声をかけたり話している途中でも眠り込んでしまうというのとでは、「傾眠」という表現でも意味合いが異なります。食事中にもウトウトしていることも、「日中傾眠傾向」という記録だけしか情報が無いとなかなかその後の評価につながりません。
デイサービスの連絡帳など、ご家族などに様子を伝える時の「傾眠」の表現はNG
傾眠という言葉は、介護や看護の業界用語で、一般の人にはいまいち伝わらない言葉です。「本日はずっと傾眠傾向でした。」とご家族に伝えたとしたら、「眠気が強かったのかな」と思ってくれる人もいると思いますが、「傾眠って何!?」とネットなどで調べて、意識障害の一種のようなものが出てくるとびっくりしてしまうと思います。介護看護業界内でもあま「傾眠」という言葉を使うべきではないですが、一般の人に伝える時はより言い方を変えて、具体的な出来事として伝えるようにしましょう。例えば、「午前11時ころからウトウトしているご様子だったので、15分に1回くらいお声かけしましたが、横になりたいと希望がありましたので横になっていただきました。」のように書いた方が、みんなに伝わりますし、介護・看護のスタッフのかかわりやその日の過ごし方が具体的にわかります。
まとめ
「傾眠傾向」とは、高齢者によく見られる軽度の意識障害の一種で、外部から軽い刺激で意識を取り戻す状態を指します。傾眠は意識障害の4段階のうち最も軽度であり、昏迷や昏睡などの状態よりも軽いです。
傾眠傾向の要因には、認知症、脱水症状、慢性硬膜下血腫、内科的疾患、薬の副作用などがあります。特に認知症では無気力状態や睡眠リズムの乱れが傾眠を引き起こす可能性が高く、脱水症状や薬の副作用も傾眠の原因となります。
傾眠傾向が見られた際には、話しかける、日中に体を動かす、こまめに水分補給する、薬の調整、食事を見直す、見守る・支える、時間を決めて昼寝をするなどの対策が取られます。注意すべきトラブルとしては、食事中の誤嚥、転倒や転落のリスク、食欲低下などが挙げられます。
傾眠傾向は高齢者によく見られる症状でですが、介護記録や看護記録では、「傾眠」という用語を使う場合には、状態を記録して伝えることと合わせて、その状態が起きている原因について医師や看護師と協力してできるだけ安全な状態にできるように前向きに情報交換していくことが大切です。意識が低下している状態で過ごすことは、ご利用者・患者さんにとってもフワフワしていてしんどい状態ですし、転倒や転落などのリスクも大きくなるので注意していきましょう。
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)