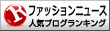先週の「北京専条」をご確認下さい。
この前文、
「台湾の生蕃が日本国民に無謀な害を加えたため、
日本国は、この生蕃を問い詰めるべく、兵を派遣しました。」から
清朝側は無謀にも害を加えられた琉球藩種子島の島民を
明らかに「日本国属民(日本国民)」と認識・規定しました。
条文には明確に琉球藩は日本国に属すと記述されていませんが上記から自明になります。
「台湾」については
「三 前略 台湾の生蕃については、中国が適切な手段で抑制」とあり、
清王朝が支配の及ぼしますと約束し「化外」でなくなり、清朝に属する「邦土」に。
日本側は台湾を「主権者のいない無主の地」から清王朝の「領土」と認定しました。
これにて一件落着、めでたし・めでたし、「占め子の兎」となるのです。
琉球国は日本国の国民、及び、国土と清朝がお認めになったのです。
ところがどっこい、そうは問屋が卸さなかったのです。
清朝は北京専条の前文を無視?
清王朝への朝貢国・琉球の日本のみ属すると承認したわけではない立場を取りました。
清朝の論理では条文を交わせど、朝貢国はすべて清王朝の属国(=邦土)と。
従って、琉球はあくまでも清朝、及び、日本、両国の属国(両属)との姿勢です。
日本の「国民・国家」論理展開と、清朝「冊封・朝貢」体制とは相容れないのです。
それよりも忘れてはならじ!
琉球国本体は今までの経緯にどのような思い・考え・対応したかの事実です。
そもそも、江戸時代初期、薩摩藩に支配されるまでは両属ではなく、
明朝の冊封・朝貢国ながら、歴(れっき)とした「王を頂く国」に違いありません。
1429年頃、三国(北・中・南)に分離していた沖縄本島を中山王が統一、
明朝(1368~1644)の冊封体制下に組み込まれ中継交易でめっぽう栄えました。
ところが、薩摩藩主・島津家久の数々の要求事項を拒否し続けた為、
1609年薩摩軍に首里城まで侵攻されやむなく和睦、薩摩藩の従属支配下に置かれる羽目に。
(薩摩藩には貢納、江戸幕府には慶賀使節等々を負わせられます。
更に、琉球国はこの事実を明朝には伝えていません。)やがて、明朝が滅び、
清朝(1644~1912)が中原・江南を統一、明朝と同じく清朝の冊封体制下に入ります。
続く。
この前文、
「台湾の生蕃が日本国民に無謀な害を加えたため、
日本国は、この生蕃を問い詰めるべく、兵を派遣しました。」から
清朝側は無謀にも害を加えられた琉球藩種子島の島民を
明らかに「日本国属民(日本国民)」と認識・規定しました。
条文には明確に琉球藩は日本国に属すと記述されていませんが上記から自明になります。
「台湾」については
「三 前略 台湾の生蕃については、中国が適切な手段で抑制」とあり、
清王朝が支配の及ぼしますと約束し「化外」でなくなり、清朝に属する「邦土」に。
日本側は台湾を「主権者のいない無主の地」から清王朝の「領土」と認定しました。
これにて一件落着、めでたし・めでたし、「占め子の兎」となるのです。
琉球国は日本国の国民、及び、国土と清朝がお認めになったのです。
ところがどっこい、そうは問屋が卸さなかったのです。
清朝は北京専条の前文を無視?
清王朝への朝貢国・琉球の日本のみ属すると承認したわけではない立場を取りました。
清朝の論理では条文を交わせど、朝貢国はすべて清王朝の属国(=邦土)と。
従って、琉球はあくまでも清朝、及び、日本、両国の属国(両属)との姿勢です。
日本の「国民・国家」論理展開と、清朝「冊封・朝貢」体制とは相容れないのです。
それよりも忘れてはならじ!
琉球国本体は今までの経緯にどのような思い・考え・対応したかの事実です。
そもそも、江戸時代初期、薩摩藩に支配されるまでは両属ではなく、
明朝の冊封・朝貢国ながら、歴(れっき)とした「王を頂く国」に違いありません。
1429年頃、三国(北・中・南)に分離していた沖縄本島を中山王が統一、
明朝(1368~1644)の冊封体制下に組み込まれ中継交易でめっぽう栄えました。
ところが、薩摩藩主・島津家久の数々の要求事項を拒否し続けた為、
1609年薩摩軍に首里城まで侵攻されやむなく和睦、薩摩藩の従属支配下に置かれる羽目に。
(薩摩藩には貢納、江戸幕府には慶賀使節等々を負わせられます。
更に、琉球国はこの事実を明朝には伝えていません。)やがて、明朝が滅び、
清朝(1644~1912)が中原・江南を統一、明朝と同じく清朝の冊封体制下に入ります。
続く。