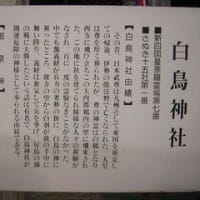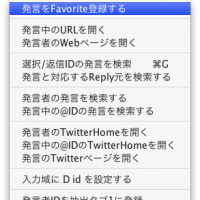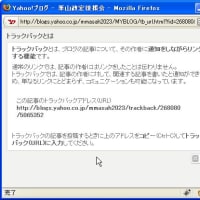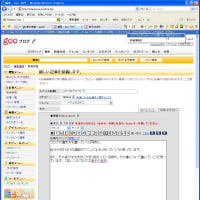エイズ、HIVはいつ危険な存在になったのか。
1940年代から50年代のニューモシスチス肺炎に着目。普段は無害だが免疫が衰えると制御不能となる。
オランダのとある助産婦訓練学校の一棟にて。
その発病タイミングから母親からの遺伝ではない。
伝染性であり、おそらくは一人の成人男性が母子に感染させ、そして殺菌不十分な注射針が
次から次へと感染を広げていった。
この時、死亡したのは三分の一。今考えるとありえないほどに弱いものだった。
HIV感染が一気に広まったのは1980年代だ。性行動の大きな変化があったとも考えにくい。
なんらかの理由でHIVそのものが変化した、粘り強くなった。
情勢が一気に変わるティッピング現象において粘りの重要性はこのように考えられる。
強い印象があり、そして頭にこびりついて離れなくなる。
つまり「記憶に粘りつく」
ウィンストンのフィルター付きタバコの例。
Winston tastes good like a cigarette should.
本来asを使う所にlikeを使う。どこか挑戦的な印象。
文法無視ではなく、口語表現なのだと言いはったという。
さて、一気に商業上以上の成果を収めた宣伝文句自体はどういう意味合いがあるのだろうか。
それが「粘りの要素」と題した第三章。ちょっと変えるだけで大きく結果が異なる
メッセージを創る手段。おっと、ここはまだ一章。原則2。次は原則3の背景の力です。
私の感想。
日本語はひらがな、カタカナ、漢字、各種外国語のどれもこれもが使え、
そして語順もかなり自由が効く。それでも今もって当然とされる文法は存在し
意識せず常識としている。それをあえて少しだけ外した言葉。
どこか少しだけ言葉遊びのような。
粘り、を繰り返しととればコンビニなどのレジで使われる丁寧語と尊敬語と謙譲語が混ざったような
不思議なマニュアル言語もそうなのかもしれない。
あれもきっと教える側としては日常と少し異なるがゆえに「正解」を教え込みやすく
そして客側も日常とは異なる店員との商行為としてのテンプレートを半ば強要される。
今は既にある程度改善されたようだけど。コンビニ等に繰り返し行くことで
どこか日常の中に「よそよそしさ、仰々しさが当たり前」になってしまったりはしないのかな?と思いつつ。
1940年代から50年代のニューモシスチス肺炎に着目。普段は無害だが免疫が衰えると制御不能となる。
オランダのとある助産婦訓練学校の一棟にて。
その発病タイミングから母親からの遺伝ではない。
伝染性であり、おそらくは一人の成人男性が母子に感染させ、そして殺菌不十分な注射針が
次から次へと感染を広げていった。
この時、死亡したのは三分の一。今考えるとありえないほどに弱いものだった。
HIV感染が一気に広まったのは1980年代だ。性行動の大きな変化があったとも考えにくい。
なんらかの理由でHIVそのものが変化した、粘り強くなった。
情勢が一気に変わるティッピング現象において粘りの重要性はこのように考えられる。
強い印象があり、そして頭にこびりついて離れなくなる。
つまり「記憶に粘りつく」
ウィンストンのフィルター付きタバコの例。
Winston tastes good like a cigarette should.
本来asを使う所にlikeを使う。どこか挑戦的な印象。
文法無視ではなく、口語表現なのだと言いはったという。
さて、一気に商業上以上の成果を収めた宣伝文句自体はどういう意味合いがあるのだろうか。
それが「粘りの要素」と題した第三章。ちょっと変えるだけで大きく結果が異なる
メッセージを創る手段。おっと、ここはまだ一章。原則2。次は原則3の背景の力です。
私の感想。
日本語はひらがな、カタカナ、漢字、各種外国語のどれもこれもが使え、
そして語順もかなり自由が効く。それでも今もって当然とされる文法は存在し
意識せず常識としている。それをあえて少しだけ外した言葉。
どこか少しだけ言葉遊びのような。
粘り、を繰り返しととればコンビニなどのレジで使われる丁寧語と尊敬語と謙譲語が混ざったような
不思議なマニュアル言語もそうなのかもしれない。
あれもきっと教える側としては日常と少し異なるがゆえに「正解」を教え込みやすく
そして客側も日常とは異なる店員との商行為としてのテンプレートを半ば強要される。
今は既にある程度改善されたようだけど。コンビニ等に繰り返し行くことで
どこか日常の中に「よそよそしさ、仰々しさが当たり前」になってしまったりはしないのかな?と思いつつ。