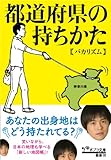社会で生きていくのに重要なことは
人とコミュニケーションをとることです。
人とコミュニケーションをとるのに重要なのはことばです。
ことばは「話しことば」、「書きことば」
それから比喩的に言うと「顔で話すことば」
の3種類があると思っています。
「顔で話すことば」というのは変な表現ですが
簡単に言ってしまうと表情です。
例えば友だちや知り合いにメールを送るときに
顔文字をつけたりしますよね(^_^)/
今笑顔で手をあげている顔文字を文章につけてみました。
笑顔だということは気持ちがプラスだということを表しています。
顔文字というのは人間の心理を比喩的に表している
言語だということができるはずです。
このように顔の表情というのは非常に重要なのです。
そこで単純に言語を教えるだけでなく
子どもには表情豊かになるように
日頃から気をつけていってほしいと思います。
無表情なのは危険ですね。
さて、話が横道にそれてしまいましたが
いろいろな科目があるなかで
私が一番重要だと思っているのは国語です。
塾では算数や数学が重視されますが
大人になってから一番必要なのは
言語表現が豊かであることです。
人といれば会話をします。
会話というのはふつうは言語を用います。
ものを考えるときに
人間は言語を用います。
言語によって人は
コミュニケーションをとることができ
考えることができるわけです。
だから言語を磨くには
国語が重要だというわけです。
(これは他科目を軽視するという意味ではありません)
国語は答えの出にくい科目だから
勉強しにくいというのは
国語を受験の道具だと思っているからです。
受験国語ははっきり言ってムダが多いです。
受験国語の勉強をして
国語力がつく人間が現代の世の中で
どれだけいるというのでしょうか。
私が一番嫌いなのは(これは偏見もありますが)
選択肢から正しい答えを選ぶ問題です。
これが国語をつまらなくしている
大きな要因であることはまちがいないと勝手に思っています。
国語の勉強で重要なことは
言語あるいは文章の意味を解釈すること
そして、自分の考えや気持ちを
言語で表現すること
の2つです。
例えば芥川龍之介の「羅生門」という作品がありますが
それを読んだときに
「下人の気持ちをあとのア~エから選びなさい」
なんて問題があったらちょっと待てよ
と私は言いたいです。
それよりも
「自分がこの場面にいたらどうするか」
という問題を理由もつけて答えさせたほうが
よほど面白いです。
なぜなら国語というのは
唯一の答えがない学問だからです。
(知識を除く)
そんなわけで
現代の言語教育について
私は疑問を持っているわけですが
さて、どうすればいいのでしょうか
というのが正直なところです。